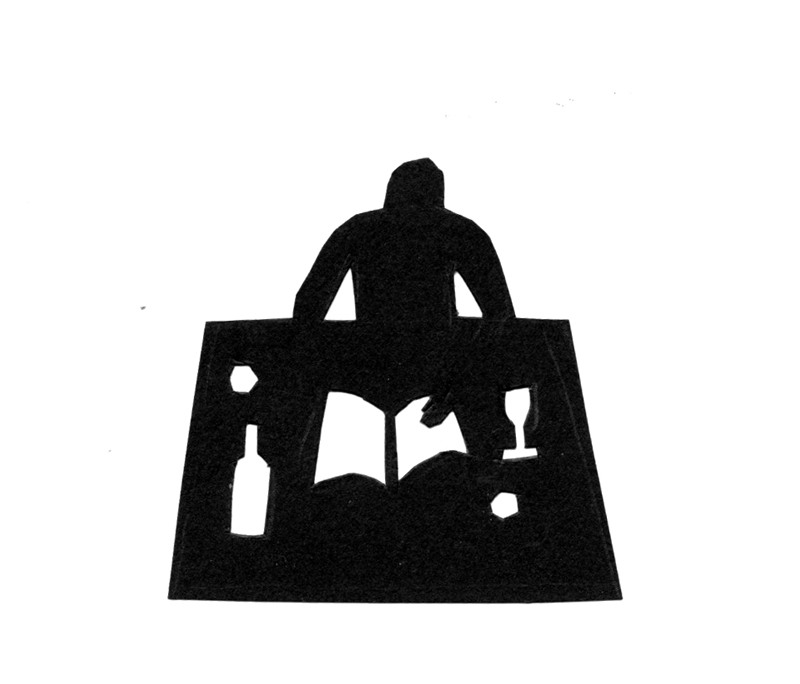18世紀の哲学者ルソーは、独特の教育書『エミール』(1762年)で、子どもを「肉食動物」にしないことが大切だと説いている。興味深いのは、それが栄養学とは違う視点で論じられていること。
「それはかれらの健康のためにではないにしても、かれらの性格のためにだ。経験をどんなふうに説明してみても、一般に肉をたくさん食う者がそうでない者より残酷で兇暴であることはたしかなのだから」(今野一雄訳)。そして、イギリス人、古代ペルシャのゾロアスター教徒、未開人、はたまたホメロスの『オデュッセイア』に出てくる巨人やら北アフリカに住んでいた民族などを引き合いに出して、やや極端に思える自論を展開。
さらに、ギリシアの著作家プルタルコスが書いた文章を長々と引用している。「ピタゴラスはなぜ獣の肉を食うことをさしひかえていたのか、ときみはたずねる。しかし、わたしは反問しよう。殺した肉を自分の口にもっていき、息たえた獣の骨を歯でかみくだき、死んだ肉体、死骸を自分のまえにもってこさせ、さきほどまでないたり、ほえたり、歩いたり、見たりしていたものの肢体を胃袋のなかにのみこむ、そういうことを最初にした人はどれほどの勇気をもっていたのか」。ここからの一節をうっかり熟読などしようものなら、しばらくの間は肉を口にするたびに複雑な気持ちになってしまいそう。
現代では、心身の健康のためだけではなく、地球環境のためにも肉を過剰に食べるのは考えものだろう。とはいえ、肉に限らず、特定の食品をやり玉にあげるのはいかがなものか。「食」の背景には、民族や家族、個人の文化や歴史が詰まっているのだから。
ルソーが肉食を攻撃する態度からは、かたくなな性格が見え隠れする。私生活でなにかと苦労続きだったのも、偉大な作品を残したのも、そんな性格がもたらした結果かも?(さ)