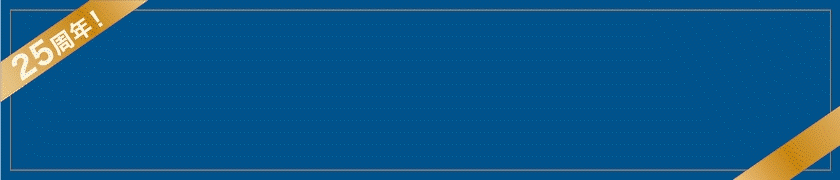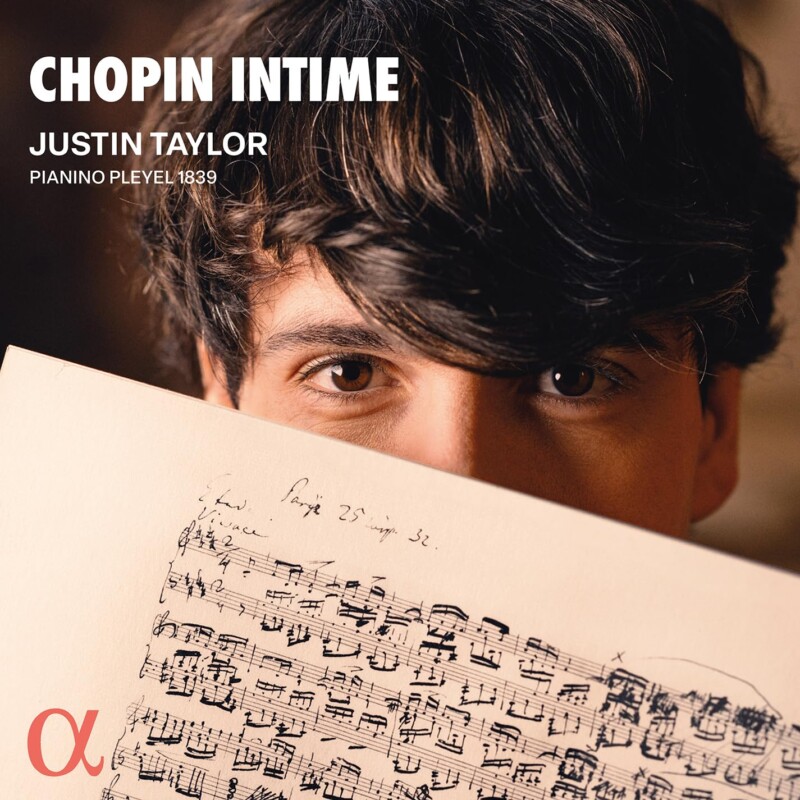ガエル・ファイユの初小説『プティ・ペイ』を読む

今これを書いている時点で、ガボンの8月末の大統領選挙後の激しい暴動の報道が続いている。悲しいかな珍しいことではない。アフリカのある国々では,恒例事のように選挙の後クーデターや暴動が起こり、おびただしい死傷者が出る。これは土地柄ではない。何かが異常なのだ。この小説はこの異常さを少なからず解き明かしてくれる。
『プティ・ペイ』はガエル・ファイユの初の小説である。1982年ブルンジで生まれた34歳の青年は、数年前から音楽アーチスト(ラッパー/スラマー/ヒップホップ)としてメジャーの会社から作品を発表している。父親がフランス人、母親がルワンダ人の混血である。母親がベルギー人で父親がルワンダ人のスター歌手ストロマエとどこかしら共通項のある佇(たたず)まいだが、ストロマエは父親がその「歴史」の中にいたのに対して、ガエル・ファイユは自分自身がその中にいた。
小説は話者ガブリエル(愛称ガビー)の少年時代(10歳から13歳)の物語である。1990年代前半のブルンジが舞台で、北にルワンダ、西にザイール(現在のコンゴ民主共和国)を隣国とする小さな国(プティ・ペイ)である。父親は兵役時代にこの地にやってきて、アフリカを愛してしまった「ババ・クール」な白人フランス人実業家。母親はルワンダ人で、60年代のツチ族迫害を逃れてブルンジに移住してきた。二人は愛し合い、二人の子供(ガビーと妹アンナ)をもうけた。状況がどうあろうがアフリカの夢を追い続けたい父と、故国帰還の夢と子供たちの安全確保という相反する思いに悩む母の関係は悪化し、やがて母は別居してしまう。
小説のプロローグで父ミシェルが幼いガビーにフツ族とツチ族の違いと、なぜ両者は戦争するのかを説明している。両者は同じ土地に住み、同じ言語を話し、同じ神を崇めているが、両者は同じ鼻の形をしていないから戦争をする、と。短身で丸い鼻をしたフツ族、長身で長い鼻をしたツチ族、どちらでもいいような違いが、政治と歴史によって厳しい民族区分になり、この世界にはフツ族かツチ族かしかなく、何人たりともこの二つのうちのひとつに帰属することになる。つまり敵か味方か。敵ならば殺す、味方ならば敵を殺せ。この地の歴史は加速度的に憎悪を膨張させて大悲劇へ向かう。
少年ガビーの日々は,歩み寄る大悲劇の予兆、父母の破局という波風を受けながらも、ブジュンブラ(首都)の特権階級の住宅街に住み、近所の裕福な悪ガキたちと徒党を組み、盗み/喫煙/飲酒その他やりたい放題。タンガニーカ湖、ンタアングワ川にはカバやワニもいる。マンゴやイチジクの実る林。楽園のような環境で、フツもツチもなく遊んでいた幸福が急速に脅かされていく。11歳の盛大な誕生パーティー(ワニ肉のバーベキュー)を幸福のクライマックスとすれば、それに前後する1993年6月のブルンジ大統領選挙に伴う政変劇は地獄への急降下の始まりだった。初めての民主的選挙はクーデター、大統領暗殺、軍政、戒厳令へ。ガビーが拠り所にしていた悪ガキ4人組も、しだいに政治的ポジションを明らかにすることを余儀なくされ、ガビーはそれを嫌い孤立する。
この孤立の時期に、少年はギリシャ人老婦人と知り合い、彼女の所蔵するおびただしい数の書物に魅せられ、にわかに本の虫になっていく。政変と紛争の現実から逃れられる唯一の場所がこの書庫だった。本による救済という感涙を誘うエピソード。だが、少年たちとの友情や、妹と家族を守らなければならないという「男気」が、ガビーを否応なく突き動かしてしまう。悪ガキたちは住んでいる地区は自衛しなければならないと政治に首を突っ込み、武器を持ち、ツチ族派として過激化してしまう。ガビーは最後までその選択を躊躇(ちゅうちょ)し、抵抗し、ツチでもフツでも白人でも黒人でもない混血の子供というアイデンティティを死守しようとするのだが、歴史の悲劇は13歳でガビーにそれを断念させる。ツチかフツかどちらかを選ばなければ、妹と父親は亡きものになる、という脅迫の前に、ガビーは13歳で遂に敵(かどうかわからない誰か)を虐殺することを選ぶのである…。
小説はその後フランスで育って大人になったガブリエルが20年後にブルンジの日々の「落とし前」をつけるために少年の地に帰るというものである。ラップ、ヒップホップの言葉の使い手であるガエル・ファイユの文体は、その少年の日々の幸福を描くときのテンポの良さ、ノリの良さは、読んでいて「名調子!」と膝を打ちたくなるほどのうまさである。小説の前半はたとえ大虐殺の予兆があろうとも、アフリカのリズムやユーモアが極上だ。もちろん白人入植者は程度の差はあれ、みんなレイシストで、紛争がどんなにひどくなって周りに死者がゴロゴロいようが、それよりも自分の愛玩動物の方が大切だったりする。皮肉もブラックユーモアも実際に少年の目で見たもの。「キャバレー」と呼ばれる、誰も顔が見えないほどの暗がりでアルコールを飲む場所で、無名の人々が誰はばかりなく自分の愚痴や意見を言い合う。ブルンジにもこんな場所があり、隠れた民主主義は厳然と存在する。その場所こそ、この小説の最大の救いであることは小説の最後でわかる。9月6日、2016年度ゴンクール賞候補の一つに選ばれた。応援しています。
文・向風三郎