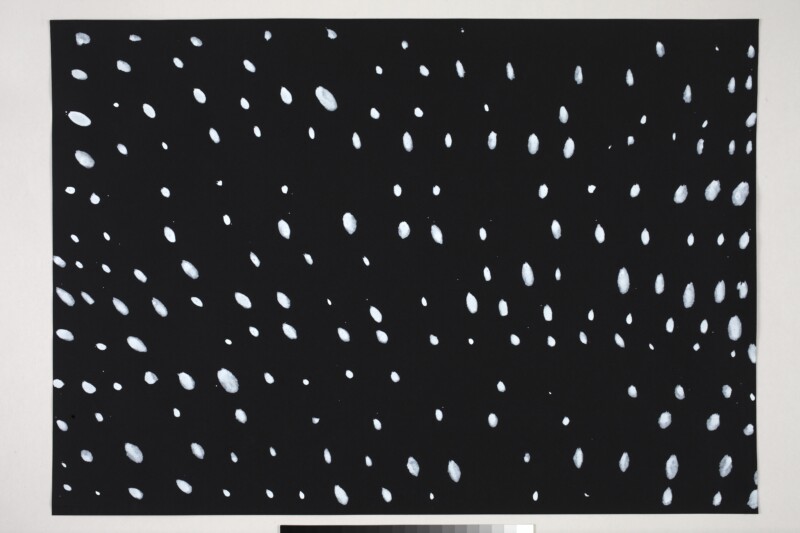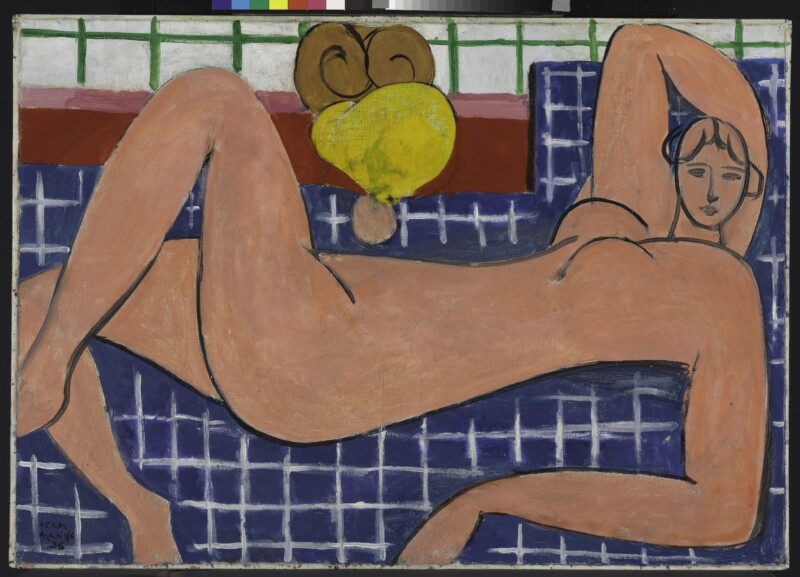イドリサ・ギロとメラニー・パヴィーの共同監督作品『Cendres/灰』は、全編を通してゲッソォ・明子さんという女性を追うドキュメンタリーです。ペール・ラシェーズ墓地で遺灰を納めた壺を受け取る手続きをするシーンから映画は始まります。母、ゲッソォ=小坂恭子さんの遺灰です。明子さんは母の住んでいたパリのアパルトマンで遺品の整理をしていて母が娘に残した日記を見つけます。この日記に書かれていたことを起点に、広島に生まれ60年代に東京の大学で時代の洗礼を受け、ピエール=ドミニク・ゲッソォというシネアストと知り合い、彼の映画に出演し、やがて彼とともに海外に飛び立った母、恭子さんの人生が浮かび上がって来ます。恭子さんの20代の姿を収めた映画の断片の中に当時の一人の日本女性の生き様を垣間見る思いがします。恭子さんがやって来たフランスの映画界はヌーヴェル・ヴァーグのまっただ中、彼女はゴダールやトリュフォーといった映画人と交友をもち、映画(ゴダールの『メイド・イン・USA』等)に出演したりもします。しかしアジア人である自分がこの地で女優をつづけることの限界を感じます。明子さんは遺灰を抱いて、広島の母の実家へ赴きます。明子さんはパリの親元を離れ、東京で暮らすようになって16年。それでも「外国で生まれ育った彼女は日本のしきたりを知らないから皆で見守って彼女を日本人にしてやって下さい」などと言う親戚のおじさんの言葉が、筆者にはちょっとした衝撃でした。しかし明子さんは素直にその言葉を聞いていました。映画の中で明子さんは自分のことはいっさい語りません。ひたすらこの映画とともに、生前に知り得なかった母のことを理解しようと努めているように思えます。分骨ならぬ分灰の儀式を済ませ東京に戻った彼女は、母のことを知る人を探し、会いに行きます。
映画は、手元に残った母の遺灰を海上に撒きに行く明子さんの表情を捉えたクローズアップで終わります。充分に、そして素直に愛を交わし合うことが出来なかった母と娘。そんな母に対する明子さんの喪の仕事は終わったのでしょうか?映画の中では語られないものの、ハーフとして生まれた自分のアイデンティティを自問している彼女も感じました。筆者にとって、そして少なからぬOVNIの読者にとって、人ごととは思えない映画です。(吉)