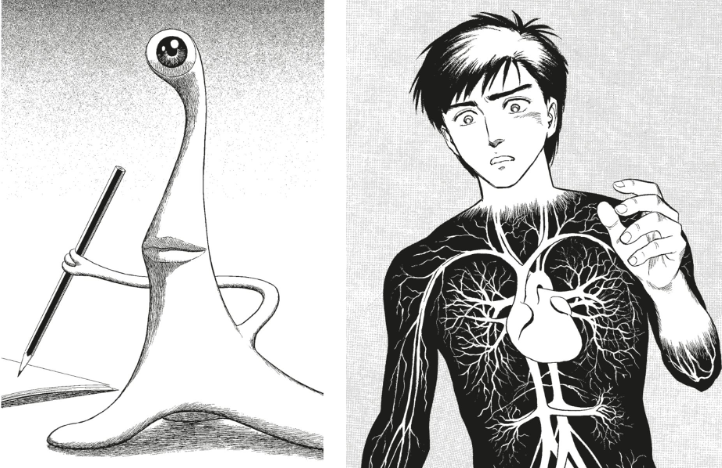オランド大統領の60の公約の31番目は「同性同士の結婚と養子縁組」。1999年、同性カップルにも適用された〈市民連帯協約 PACS〉の是非論が世論を二分したように、この公約に関しても議論が沸騰。10月23日、全国大都市で保守系市民が「子どもを守るため」同法案反対デモを行った。
古代からの社会規範であり、カトリックの7つの秘跡の一つ〈結婚〉の慣習をくつがえす改革案であるだけに、同性同士の結婚の合法化案は11月7日の閣僚会議後、来年1 月以降に国民議会で成立すれば、30年前ミッテラン大統領が死刑廃止を実現したのと同様の歴史的改革となる。
フランス人の75%は同性同士の結婚に賛成しているが、彼らに養子縁組を認めるかとなると66%(極右FN支持層84%/保守UMP系77%)が国民投票にかけるべきと答えている。南仏オランジュのボンパール市長を始め、かなりの市町村長が公務違反となっても同性同士の結婚式は執り行わないと表明。その場合は助役が代役を務めるのだそう。
同性同士の結婚は、すでに10カ国(オランダ、ベルギー、スペイン、カナダ、南ア、ノルウェー、スウェーデン、ポルトガル、アイスランド、アルゼンチン)で合法化されており、オランダは彼らの養子縁組も認めている。しかし子どもは父と母を必要とし、同性同士の家庭で子どもの健全なアイデンティティが形成されるのか…と実例の少ない中で精神・心理学者らも懐疑的。カトリック系保守派の旗手、クリスチーヌ・ブタン元UMP議員などは、「ゲイ同士が結婚すると男同士の家庭となり小児性愛、近親相姦が続出するだろう」と、しきりに警告を発している。
こうした背景には、フランスでは1982年に同性愛が非処罰化され、同性愛が精神病のカテゴリーから外されたのも1992年にすぎず、長い間、同性愛を「社会のガン」とみなした偏見が根強いからだろう。最近のIFOP調査によれば、日曜のミサに行く人は65歳以上でも15%、25〜34歳は1 %と、教会での結婚や洗礼式がまれになっている。同性同士(2000:24%、2011:4.4%)でも市・区役所に届けるだけで結ばれ、いつでも解消できるパクスが一般化している反面、大都市では婚姻者の半数が離婚し、子どもの2人に1人は婚外児だ。日本風に言えば、バツイチ、バツニ同士による複合家庭が増えている。結婚という概念が薄れつつあるのとは逆にゲイ、レズビアンらの結婚願望の高まりは、性的志向が異なっても社会の一員として認められるための闘いの現れなのだろう。
9月にトビラ法相が「同性同士の結婚と養子縁組」法案を明らかにしたが、10月10日エロー首相は、同性カップルの親子関係は養子縁組の場合しか認めず、代理母出産やレズビアンの人工授精による出産などは認めないと表明。今後、同性愛者たちの根強い運動と、彼らに育てられる児童の健全な成長が社会の疑心に答えてくれるのでは。
最近テレビでも、どちらかの養子または実子を同性同士で仲良く育てている姿を紹介している。一般家庭での家庭内暴力や近親姦、そして離婚・別離後の片親家庭が急増する中で、相思相愛の同性カップルが築く新しい家庭は、21 世紀文明の一要素となるのかもしれない。新しい社会規範を政治がどのように導いていくかだろう。(君)