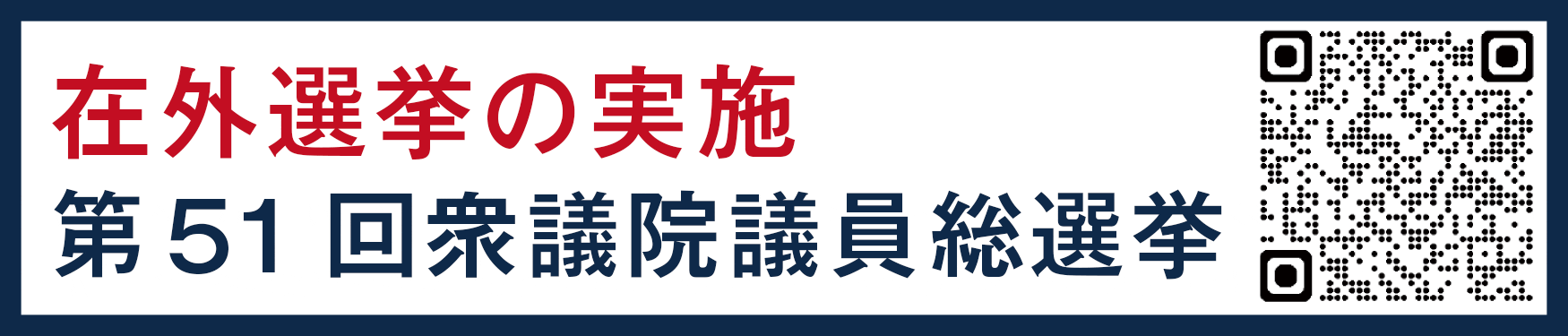ゾラは『居酒屋』で作家としての名声を確保した。その続編が、この作品の主人公の娘の名前が題名になっている『ナナ』(1880年)だ。
パリの労働者階級の両親のもとで生れ育ったナナは、父親からは贅沢嗜好(ぜいたくしこう)を、母親から気前の良さと美食に対する情熱を引き継いだ。
美しく成長したこの娘は、女優、そして高級娼婦として、パリの上流階級の人々に近づいていく。女優デビューを果たした彼女がまずしたことは、レストランを自宅に出張させての大宴会。メニューは、蒸焼の若鶏、舌平目のフィレ、鵞鳥(がちょう)の肝臓の薄切り、ソテーしたヒレ肉、ホロホロ鳥の冷肉、イタリー風茸やパイナップルのパイなど。もちろん、シャンパンやワインが途切れることなく注がれる。その母親がそうであったように、ナナの食への情熱は年を経るごとに拍車がかかっていく。「二十日大根や砂糖焼巴旦杏(プラリーヌ)を齧(かじ)り、肉をしゃぶる、鸚鵡(おうむ)のような好みを持ったこの女は、毎月、食卓のために五千フラン費った。台所でははめを外した濫費、ものすごい無駄遣いがおこなわれ、葡萄酒は幾樽となくあけられ、勘定書は三、四人もの手を通って膨れ上がった。」(川口篤訳)このあたりからは、何かに取りつかれたように浪費しなくては気がすまないという病的な傾向が匂い立ち、読むほうは怖い物見たさで本の最後まで引っ張られることになる。
ゾラは人の3倍は食べる健啖家だったけれど、ゾラ夫人が用意する食卓からは、『ナナ』のような腐敗臭はしてこない。ゾラが初めての小説の著作権を受け取った時に夫人が用意したのは、ブイヤベース、野兎の赤ワイン煮込み、ローストチキンとサラダ。年を経るともっと凝ったものが食卓にあがることになるけれど、それらはゾラ夫人の芸術品として友人たちの喝さいを浴びるものだった。(さ)