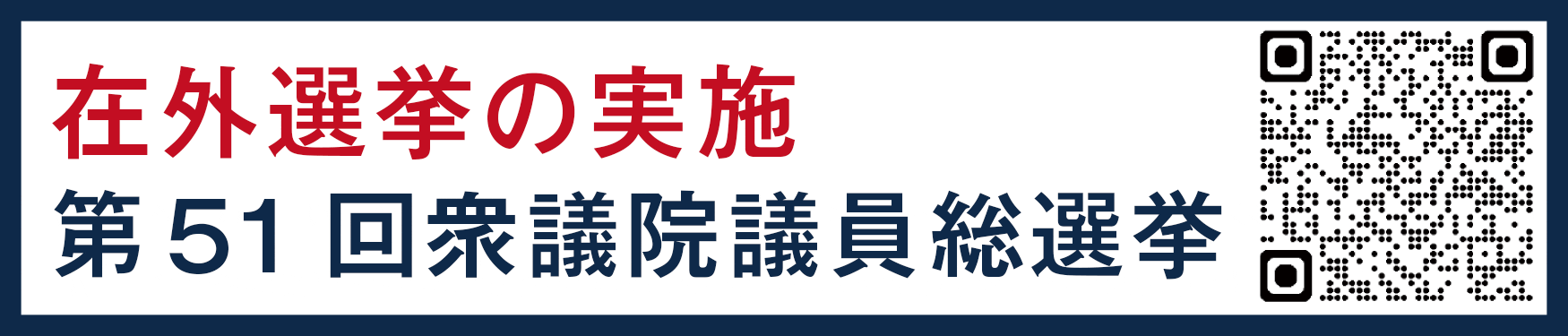ポルトガルのコミック作家、ホセ・カルロス・フェルナンデスの作品が初めて仏訳されて陽の目を見た。
ポルトガルのコミック作家、ホセ・カルロス・フェルナンデスの作品が初めて仏訳されて陽の目を見た。
セピア色の町は、ポルトガルでもどこでもない。住んでいる人の名前から判断すると東欧の町らしいが、時間や地理の軸から落っこちてしまったようだ。人の影がなく、思い出の品を捨てるためのポストや、自分の夢を投ずるユートピアのポストや、動物を催眠術にかける協会の雑誌などを並べたキオスクが街角にある。前に泊まった客の思いが部屋にしみ込み、次の客が悪夢を見てしまうホテルもある。
そこに住んでいる住人たちもどこか奇妙で、不条理な職業や趣味に取りつかれている。偶然に見た事故や出来事を書き留めて意味を探すフリューゲルホーン氏、国立集団ヒステリー調査ラボに勤務し、レコードを逆転させながら悪魔的メッセージを聞きとろうとするルゴージ氏…。特筆したいのは、彼らの顔の描写。つげ義春がのっぺり顔の中に静まることのない心を表出させたとしたら、フェルナンデスは苦渋や不安でくしゃくしゃのしわしわ顔が得意。2ページのショートストーリーが続いていくが、読み進むうちに、これらのしわしわが重なり合って、一つの、カフカの世界から抜け出してきたような人間の顔の輪郭が浮かび上がる。(真)
Cambourakis社発行。19€。