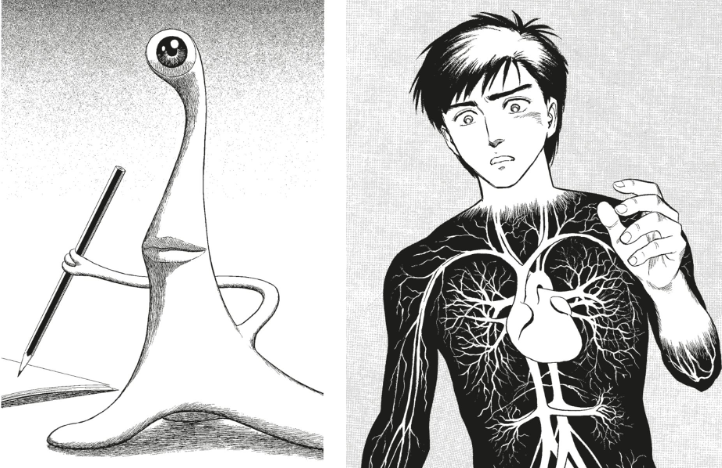ナチの廃墟が残ったまま冷戦が始まった1949年、米・英・仏を中心に12カ国が加盟し、(旧西ドイツは55年に加盟)「米国を引き込み、ロシアを締め出し、ドイツを抑え込む」ためにできたのが北大西洋条約機構NATO。しかしドゴール大統領が、米国主導のNATOとの間に一線を引くためと、フランスが核保有国になった時期と重なる1966年、その軍事機構から離脱したことはフランスの現代史に刻まれている。
ナチの廃墟が残ったまま冷戦が始まった1949年、米・英・仏を中心に12カ国が加盟し、(旧西ドイツは55年に加盟)「米国を引き込み、ロシアを締め出し、ドイツを抑え込む」ためにできたのが北大西洋条約機構NATO。しかしドゴール大統領が、米国主導のNATOとの間に一線を引くためと、フランスが核保有国になった時期と重なる1966年、その軍事機構から離脱したことはフランスの現代史に刻まれている。
冷戦終結・ソ連崩壊後、加盟国外でもNATOが軍事介入をするようになり、フランスはボスニア内戦やコソボ紛争にも参加しているのである。そしてNATOの38の機関・部会のうち36組織に籍を置き、分担金や派兵数でも加盟国26カ国中4位を占めている。この現実を裏打ちするために、1995年にシラク大統領はNATOへの完全復帰を提案している。
ブッシュ時代から親米路線を貫くサルコジ大統領のNATO復帰の決断に対して賛否両論が飛び交っている。世論調査(3/11付Paris Match誌掲載)では58%(右派76%/左派52%)が完全復帰に賛成している。反対派の中にはドゴール大統領が敷いた自主路線をないがしろにするという見方や、総軍事資金の30%しか分担金を出資してない米国がほとんどの司令部を牛耳っているという矛盾、外相時代にイラク戦争への参加を拒否したドヴィルパン元首相などは、軍事面でも米国一辺倒になることを危惧する。
3月11日、サルコジ大統領はパリ士官学校でNATO復帰についての構想を表明した。フランスは完全復帰後も自主性を保持し、核兵力は従来どおり国家の支配下に留まる。1995年からフランスは軍事委員会にも参席しており、アフガンの対タリバン戦闘にも参加している今日、現実に目をつぶり紙の上での「離脱」を守ることの「欺瞞に終止符を打つ」。加盟国の参戦は強制的ではなく、イラク戦争のようにドイツと同様に、参加を拒否することも自由であることなど。
多くの東欧諸国が欧州連合EUに属しながらも軍事的に米国の傘下にあることを望んでいるなかで、フランスがEU戦力の強化に努めていたのはNATO戦力に対抗するためでは、と疑っていたものだ。今後フランスが100%NATOに帰属することでこの疑念も解消され、同機構でのフランスの比重と発言力も増すことになるという。
3月17日、フィヨン首相は国民議会で反対派の反論を封じるために「政府信任」投票を課し、与党議員過半数の賛成を得て逃げきった。
4月4日、NATOの60周年を機にサルコジ大統領はついに完全復帰を実現、フランスはNATOの最高機関、軍事委員会の正式メンバーに戻るわけだ。ドゴールが離脱宣言したころの米ソ2極体制から、今日イスラム勢力も含む多極体制に移り、宗教・民族紛争が続出するなかで、「大国フランス」がいつまでもNATOの天井桟敷に留まっていられないこともわからないでもないが。(君)