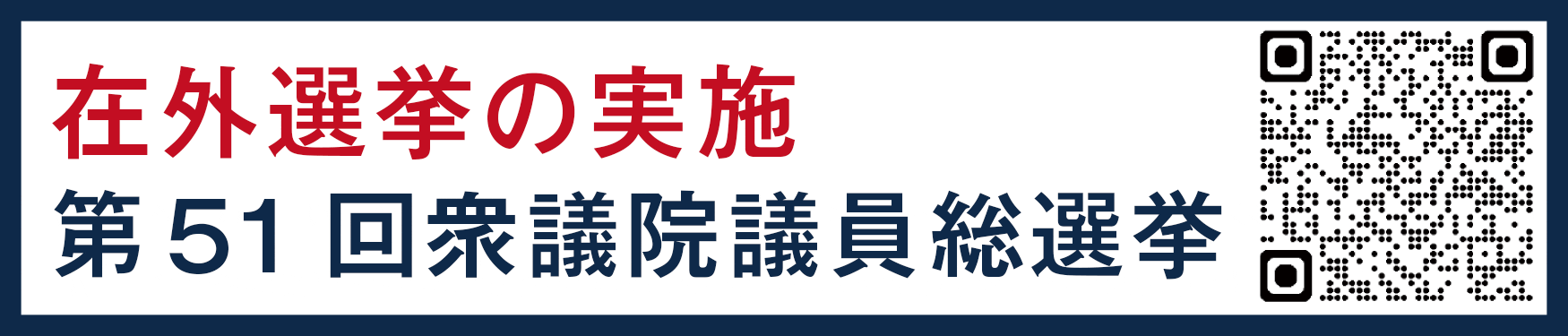| 夏休み! 大きなリュックを背負った子供たちが親に付き添われて駅のホームに集合している。さあ〈コロ〉へ出発だ。親元を離れて寝起きする3週間、子供より親の方が心配気に引率の指導員に「うちの子は…」とあれこれ頼んでいる。エリック・トレダノとオリヴィエ・ナカシュの共同監督による『Nos jours heuruex 我らの幸せな日々』は、こんな光景から始まる。主人公のヴァンサン(ジャン=ポール・ルーヴェ)は、今年初めて〈コロ〉の責任者になった。彼の父親も「まあ持っていけ」と迷惑気な息子にサンドイッチを押しつける。指導員たちも大学生のアルバイトといった感じの急造部隊で先が思いやられる。寄せ集めの共同生活が引き起こすてんやわんやの3週間。最後には「帰るのイヤ、もっと〈コロ〉にいたい」という、とびきり楽しい想い出をみんな胸にしまって解散する。 〈コロ〉Colonie de Vacances(林間あるいは臨海学校)は、2カ月もある学校の休みに、さすがに付き合っていられない親の救済策としてフランスの生活習慣に定着。お陰で親も子供も両方の立場で、それぞれの〈コロ〉体験をもっている。映画では、クロード・ミレールの『La meilleure facon de marcher 一番うまい歩き方』で描かれた二人の男性指導員の濃密な確執などが印象的であったが、『我らの幸せな日々』はもっと脳天気で、指導員たちも子供たちも恋愛にいそしむ。日本だったら指導員同士がいちゃついてたりしたら査問委員会沙汰かも知れないが、ここはフランス、それぞれの恋の行方をみんなで見守る。とまれ、いろんな性格、いろんな背景、いろんな出来事の末に部外者の侵入(教育委員会の抜き打ち視察)を、結束して乗り切って、寄せ集め集団の一体感がたかまり「帰りたくない」気持ちになって映画は終わる。(吉) |
 |
| ●Avril 修道女に育てられた捨て子アヴリルの自分探しの旅。脚本にあれれ?という弱さがあるのは否めないけれど、主役S・キントンの新鮮な魅力、N・デュヴォーシェル、C・シボニーの好演に助けられた一作。監督はジェラルド・ユスターシュ=マチュー。(海) ●ラ・ヴィレットの芝生で名作鑑賞 |
 |
|
|
|
| Robert Guediguian (1953-) マルセイユの工業地帯に生まれたロベール・ゲディギャン監督は、湾岸労働者であるアルメニア人の父とドイツ人の母を持つ。大学では社会学を専攻し、論文テーマは「労働者階級における国家意識」。生粋の共産主義者を自負していたが、政治に幻滅して、以降、映画を媒介とした社会との関わり方を模索するようになった。 1980年に『Dernier ete』を初監督。すでに失業中の若者を登場させており、以後も彼の作品には社会派的視線が目立つ。とはいえ、「誰に向けて語ったのかを忘れたような政治的映画」を否定し、観客に社会の汚さばかりを見せるより、映画という名のお伽話を提供する職人の立場も忘れない。そんなバランス感覚が最も開花した作品が、大成功を収めた『マルセイユの恋』(98)だった。その後も妻であるアリアンヌ・アスカリッドなど、おなじみゲディギャン組の役者らを、マルセイユという人生劇場に配置することにこだわってきたが、2004年には突然ミッテラン大統領を描いた『Le Promeneur du Champ de Mars』で舞台も役者も総換えし、驚かせた。 そして現在公開中の新作『Le Voyage en Armenie』では、自らのルーツをたどるかのように、舞台を異国アルメニアへと移し、監督としても新たな冒険に旅立つ。(瑞) |
 |
|
|