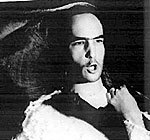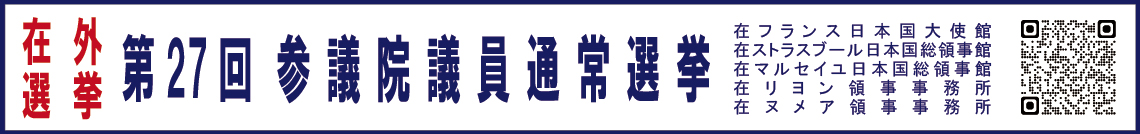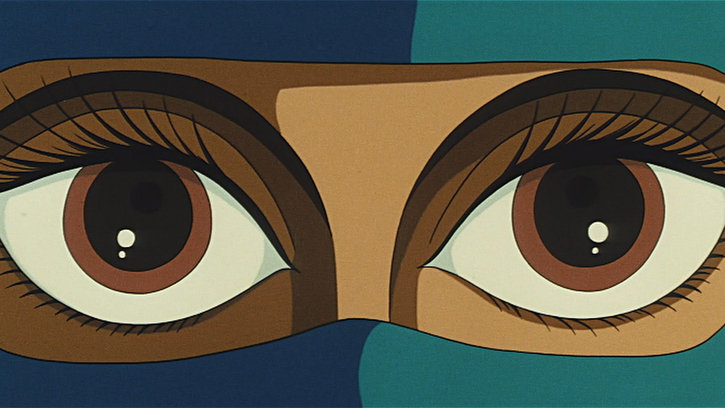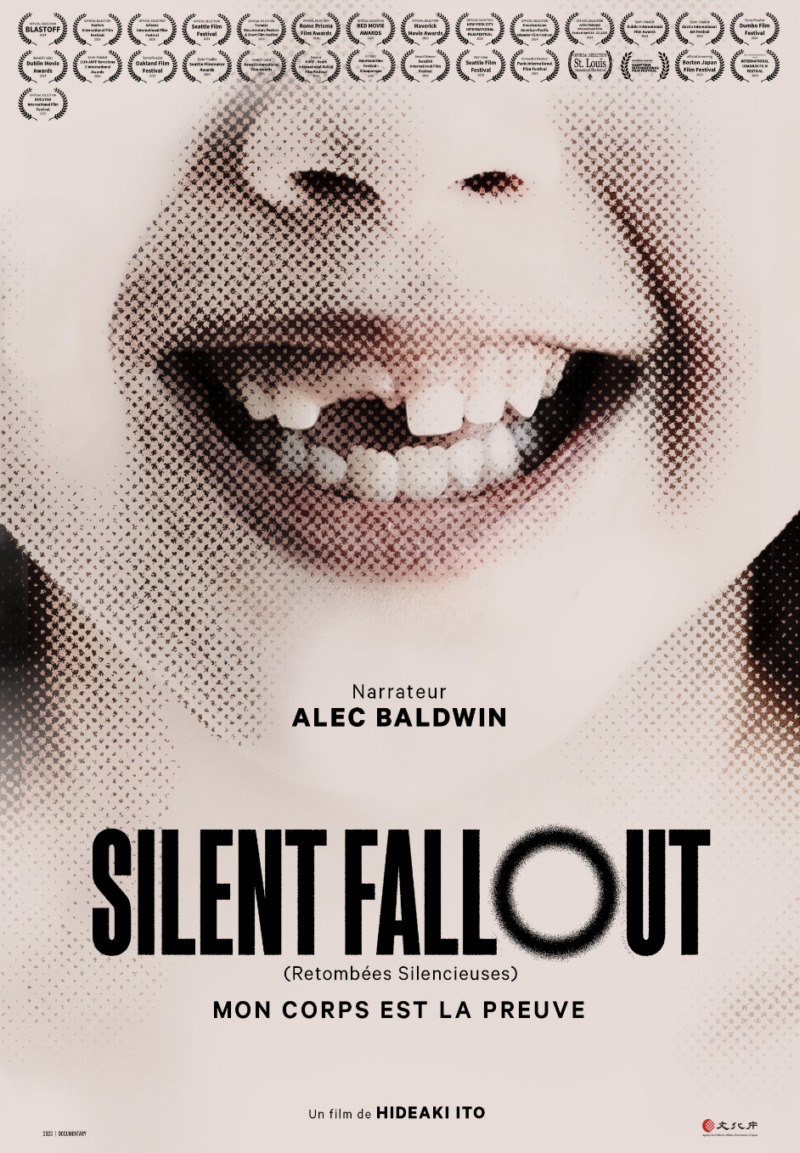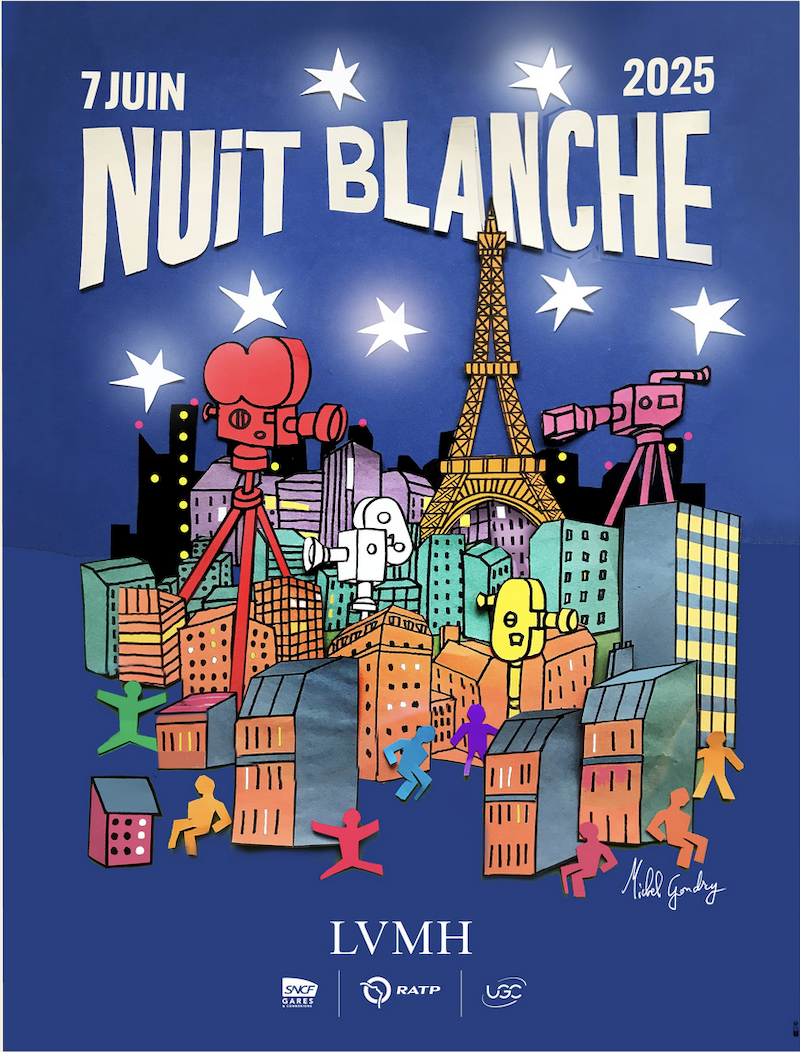『キル・ビル』、『ラスト・サムライ』と日本との縁が深いハリウッド映画に沸く東京で、11月22日から30日まで開催された第4回〈東京フィルメックス〉映画祭に通った。アジアフォーカス福岡、山形ドキュメンタリー映画祭 “アジア千波万波” 部門、東京国際映画祭の “アジアの風” 部門等々、アメリカの文化産業にすっかり侵食されている日本でもアジアの映画に目を向ける企画が各地で催され定着してきている。そんななかで〈東京フィルメックス〉は後発の映画祭だが、「”新・作家主義国際映画祭”、”コンペ” 部門ではアジアの新進作家を応援する」というカラーを打ち出している。その “コンペ” 部門の受賞作2本は確かに新鮮な驚きを与えてくれた。
最優秀作品賞の中国映画『香火』は、荒涼とした風景が印象的な僻地(山西省)で小さな寺を預かる若い僧侶が、壊れた仏像の再建のために金集めをする話。朴とつとした僧侶が、町で世俗にまみれるうちに次第に狡猾になっていくさまが、むしろ微笑ましく描かれ、急速な経済発展を遂げる中国を透視する。ニン・ハオ監督の26歳とは思えない洞察力と演出力に感心していたら、審査員特別賞は15歳のハナ・マフマルバフが13歳の時に撮影した『Joy of madness』へ。
イランの映画一家、マフマルバフ家の次女ハナが、父モフセンが製作し、姉サミラが監督したカンヌ審査員賞受賞作『午後5時に』のキャスティングの模様をDVカメラに収め73分に編集した作品だ。一家の中でこの娘が一番クールかも…。姉と父の執念の映画作りと、対象となるアフガニスタンの素人俳優候補の人たちの反応を凝視している。また、目玉企画”清水宏特集”(小津安二郎と並んで今年生誕百年)の『簪(かんざし)』(’41)が一般の人気投票による観客賞に選ばれ、清水宏・再発掘へ伏線を引いた。(吉)
最優秀作品賞の中国映画『香火』

イタリア映画の名作再公開。
ノエルのバカンス中に観ておきたいイタリア映画の名作2本を紹介。どちらもニュープリントでリバイバルです。
そのうちの1本は、ピエル・パオロ・パゾリーニ監督の『奇跡の丘 L’プangile selon Saint Mathieu』(1964)。その前々作『マンマ・ローマ』では、娼婦の母(アンナ・マニャーニ!)と思春期の息子の葛藤を、ローマ郊外の空き地を舞台に殉教劇のような痛みをこめて描いていた。この『奇跡の丘』も、神の子を宿して夫ジョゼフに疑われ、パリサイ人の迫害を避けるために家を捨て、年老いてはイエスに母であることを拒まれたマリアと、革命児としての生き方を貫いたイエス、その母と息子の愛を核にした受難劇だ。ニュープリントで、粒子の粗い画面がますますリアルになり、広野、波立つ海、風にゆらぐ木々、粗末な衣服、庶民の顔々、パン、十字架、釘、そしてイエスの怒りあふれる暗い視線が、これまで以上にボクらの心に近い。全編バッハのマタイ受難曲が流れ、この、どこまでも人間的な感動は、クリスマスのミサに出かけてもちょっと味わうことができない。
もう1本はフェデリコ・フェリーニ監督の『カビリアの夜 Les Nuits de Cabiria』。戦後の荒廃を残すローマで、カビリア(ジュリエッタ・マシーナに涙!)は男にだまされ続けながらも、無垢の魂で幸せを夢見る娼婦。オスカルに結婚を申し込まれ、全財産をみつぐが、最後は彼に崖から突き落とされる。しばし泣きくずれるが…カビリアの顔にふたたび微笑みが戻ってくる。ノーカット版。(真)