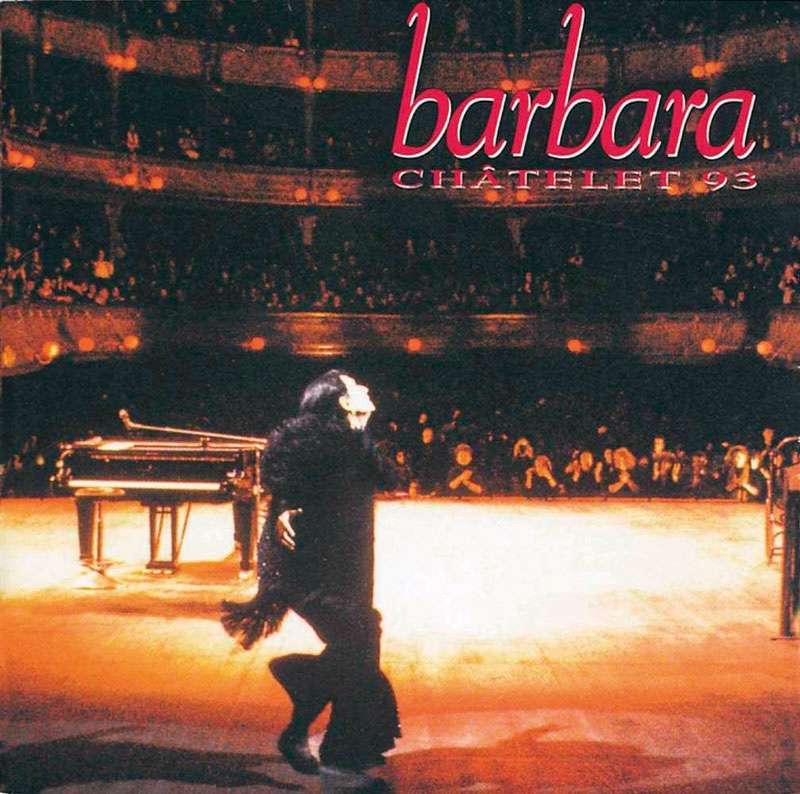日本もフランスも、新聞・雑誌を開けば映画の記事が溢れている。でもその膨大な記事の中で、的を得た、目から鱗の、適度にピリ辛の映画批評に出会うことが少なくなってきている。
《アマチュア天国!ニッポン》
日本においては映画ほど誰がコメントしても許される分野はない(自戒を込めつつ)。誰だって映画に対し何か言えるもので、誰が語ってもいいのなら、それは有名人であればなおベターと考えてしまうのがミーハー大国日本だ。大手新聞でさえ、映画を知る批評家より「あの人が観てるの?じゃあ是非!」と、名の売れた作家、タレントに副業で感想文を書いてもらう方を好む。宣伝マンは映画のチラシに「今年最高にハッピーな映画!−広末涼子」といった、有名人気に入ってますマークを刻むのに余念がない。そしてそんなチラシを「なぜにハッピー?」という疑問は持たず、ただただ有り難がってしまうのが観客。だからメジャーな媒体を占めるのは、ちょっと気の効いたことを言える有名人と、耳障りの良い言葉を紡ぎ出す便利ライター。そんなアマチュア天国にあっては、映画を知っているからこそ辛口もできる本物の批評家の出る幕はない。加えて、出る杭は打たれる国、日本では、言論の操作、辛口の抹殺は珍しくないのも問題。昨年、毒舌映画批評で評判だった井筒監督が、配給会社サイドから映画館で『オーシャンズ11』の入場を断られるという一件があった。自分も雑誌に原稿を書くため作品のスチールを配給会社に頼んだら、「ネガティブな記事の場合はスチールは貸さない」と脅されたことがある。世の中に良い映画しかない訳がないのに、ネガティブな記事を徹底的に忌み嫌い、排除するような態度が蔓延してきているのだ。不健康で気味が悪いではないか。
《仁義なきプロの暴走、おフランス》
一方、辛口は溢れているけど、本当の辛口の意味を取り違えているのがおフランス。3年前には批評家への不満を綴ったパトリス・ルコント監督の文書に端を発して、監督と批評家との間に泥沼の論争が起こったのも記憶に新しい。この時槍玉に上がったのが、『ルモンド』『リベラシオン』『レザンロッキュプティーブル』などの新聞・雑誌。それらの媒体に登場する批評は、自身も批評家であるミシェル・シモンによると、「安易な駄洒落」「暴力性」「偏見」に満ちているとのこと。「安易な駄洒落」に関しては、例えば、映画『ムーラン・ルージュ!』の紹介で、“フレンチ・コンコン”(コン=バカの意。『フレンチ・カンカン』のひっかけ)と大見出しをつけるなど。
ただ、伝統的にフランスは駄洒落を上手く使いこなすことも、知性のひとつと思っている節もあるのだが。「暴力性」なら、例えば、「更年期のスイス牛、グレン・クローズ」など肉体的欠陥をあげつらう下品さや、もしくは映画を観ていないのに、「(批評家という)職業を変えたくなる新作映画リスト」を発表するといった企画に見られる暴力性など。「偏見」なら、批評家群による監督への見解があらかじめ一致してしいることなど。『カイエ』出身の批評家がいろんな新聞・雑誌に流出しているため、例えば一般的にアサイヤス、テシネなどカイエ派の監督には甘く、ルコント、タベルニエなど職人(っぽく見える)監督には手厳しいというのが定番だ。一度ダメ監督の烙印を押されたら最後、イメージ払拭は至難の技。
以上のように「表現の自由」を盾に取り、好きな監督だけ徹底擁護、嫌いな監督なら論理的な説明不十分のまま言論の暴力を浴びせる、それが辛口を履き違えたここ10年ほどのフランス批評の傾向だ。そういえば昨年は「右翼の優等生候補、アメリ」と書いて物議を呼んだ批評家(お騒がせ男カガンスキー)もいた。目のつけどころは面白いけど、一体これが何百万という人が読むメディアに掲載すべき的を得た批評なのか、考えてしまうところだ。
《そしてポーリン・ケイルの死》
日本はアマチュアが迷走し、フランスはプロの暴走が止まらない。その結果、悲しいかな、本当の辛口批評の姿がどんどん消えていっている。でも待てよ、一体誰が批評など必要としているのか。大部分の日本人は当たり障りのない映画紹介が好きなんだし、大部分のフランス人は過激な言論が好きなのだろう。結局、誰も本当の批評など必要としていないだけなのだ。そしてそんな日本とフランスの現状を見限るように、昨年アメリカで映画愛に溢れた批評家ポーリン・ケイル(著書に『映画辛口案内』など)が死んだ。彼女の死は本物の辛口の死を暗示していたのだろうか?(瑞)