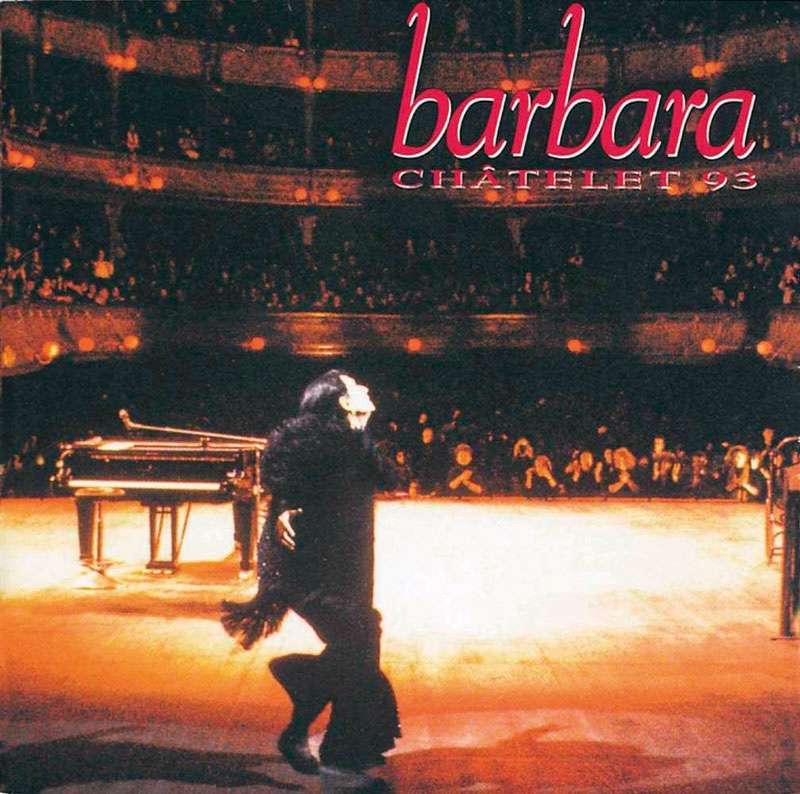生の体験
La littérature, elle, a le mérite de nous ramener
l’humain, aux soucis qui naissent devant l’opacit de l’avenir, quand on avance
l’indice de courte vue du prrésent.
生の体験
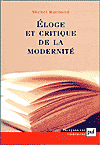 パリ第四大学の名誉教授、20世紀フランス小説、大戦間小説の専門家であるミッシェル・レモン。その専門分野、文学研究者の視点から、彼の20世紀への問いかけは2つの強調点を持つ。大戦間の文学、そして、modernitéというキーワードだ。
パリ第四大学の名誉教授、20世紀フランス小説、大戦間小説の専門家であるミッシェル・レモン。その専門分野、文学研究者の視点から、彼の20世紀への問いかけは2つの強調点を持つ。大戦間の文学、そして、modernitéというキーワードだ。
20世紀の流れは三つの大きな時代からなるとされる。つまり、19世紀から20世紀への通過、第一次世界大戦、世界恐慌、第二次世界大戦からなる大変動(cataclysme)の時代、冷戦という暗い背景を持ちながらも、経済、イデオロギー、社会における様々な戦後の「成長」が見受けられた奮起(sursaut)の時代、そして70年代以降、現代に至る幻滅(désenchantement)の時代。
こうしてとらえられる20世紀において、大戦間の重要性は、それが様々な変換のきっかけであること—戦争が最も顕著な例—、そして以降に続く流れの始まりであったことにある。こうした特徴が誰の目にも明らかなこの時代に、文学からアプローチすることは、「我々を人間的なものへ、未来の不透明を前に生まれる不安へと導く」という利点をもつ、と著者は記す。
こうして試みられるのは、様々な文学テキストを通しての哲学的考察でもなく、文学の「思想」研究でもない。文学者の文学者としての活動を通して、そして小説で描かれる人物像を介して浮き彫りにされる人間の、人間としての「人間らしさ」、そして「不安」が捉えられていくのだ。
こうしたコンテクストで、モデルニテとは、作家とその作品の登場人物たちをとりまく現実世界の現代性を指す。つまり、「産業、商業、そして絶え間ない技術発展」から定義される現代性、「炸裂と分散(éclatement et dispersion)」から定義される現代性だ。
この現代性は、各作家・作品において様々に捉えられる。産業化されていく社会と廃退していく手工業、都市社会と自然を保つ地方社会、資本階級と労働階
級、ユートピアの渇望と絶対的絶望、そして、自動車、航空、または軍事技術にみられる技術発展等、強調される点は多分野にわたる。こうした現代世界の様相は単に批判の対象であるだけではない。様々な文学作品から浮き彫りにされるのは、現代性の批評でもあり賛美でもある。
文学を介した現代性の考察は、その多様性、二重性、矛盾性を明らかにしていくだけではない。大戦間の作家たちとは、幼少期を19世紀の終わりに迎え、ベ
ルエポックの記憶を持ちながらも、青年期以降、大戦を目の当たりにした者たちである。「生の変容に強く揺り動かされた」者たちである。全ての面で断絶を体験した者たちである。そして「個人生活が社会の流れと錯綜し縺れあった」時代の者たちである。そうした意味で、現代性の様々な様相との直面は、切実である。現実世界に対して、時間的距離はもちろん、抽象的、思想的距離をもとることはできないのだ。彼らは、現在という時間の中、現代性を「生きて」いる。Céline, Aragon, Martin du Gard, J.Romains, P.Nizan, Cendrars, P.Morand, G.Duhamel等々、本書において大戦間を代表するとされる作家たち、そして彼らの作品の登場人物たちの「生」から浮き彫りにされるのは、その多様性を越えて、共通する「生」の切迫感だ。アラゴンにおけるオーレリアン、ルイ・ギユーの『Le Sang noir』におけるクリピュール、セリーヌにおけるバルダミュなど、強調される点は異なっていても、彼らの生の苦悩には共通する切迫感、存在の感覚がある。
文学体験が、文学が「人間的」であるのは、その基盤に「生の体験・感覚」があるからだ。様々な手段で過去を考えること、記憶に留めること、思考することはできるが、もはや過去は「人間的に」体験されることはない。文学はそこで我々に残された唯一の、生の体験、人間的体験の可能性なのではないだろうか。
本書はこうした「生」の、「人間的」な体験、文学体験へと、我々を誘う。
Eloge et critique de la modernit,
Presses Universitaires de France,
coll. « perspectives littéraires »,
336p., 2000, 148F
 様々な「思想家」や「批評家」が現れた20世紀フランスで、P.リクールは、おそらくは最も「哲学者」というにふさわしい。本書は、今年で88歳を迎えるリクールの、哲学者としての、個人的、「市民として」の、総括的書物だ。
様々な「思想家」や「批評家」が現れた20世紀フランスで、P.リクールは、おそらくは最も「哲学者」というにふさわしい。本書は、今年で88歳を迎えるリクールの、哲学者としての、個人的、「市民として」の、総括的書物だ。
本書は、表題にあるように、「記憶、歴史、忘却」という三つのキーワードを軸に、そして記憶の現象学、歴史の認識学、歴史条件の解釈学という三つの主要問題を枠にして、三部から構成される。600頁を越える本書の試みは壮大であり、哲学者リクールの博学は、取り上げられる思想家たちを一見するだけで明らかだ。アリストテレス、プラトン、聖アウグスティヌス、カント、フロイト、モース、デリダ、レヴィナス、フーコー等々、哲学にとどまらず、言語学、人類学、歴史学、精神分析学、社会学と、多様な思想が三つのキーワードを取り巻く。これは彼の博学の広さを示すだけではない。他者の思想は試金石として、対話相手として、本書におけるリクールの問いかけを深め、進めている。
この対話の主題は、「我々がいかに過去と関わるのか?」という問いであるといえよう。この問いにおいて、記憶と歴史が二つの軸となるのだ。
記憶の問題は、「何を」記憶は留めているのか?「誰が」それを記憶するのか?「如何に」その者がそれを記憶するのか?という一連の問いへと発展する。歴史の分野では、歴史とはエクリチュールであるという観念のもとで、歴史資料、歴史理解、歴史の記述という問題が扱われる。
記憶と歴史、厳密に言えば、記憶の現象学と歴史(記述)の認識学、この二つの軸は、両者に共通する「過去の表象(represen-tation)の問題」において交わる。つまり、過去が如何に、一方では記憶として現れ、一方では歴史として表されるのかという問題である。こうして、歴史、記憶の両者において、最も広い意味での「イメージ」の問題、義務、公正の問題、習慣(us)と乱用(abus)の問題が取り上げられる。 こうして、第三のキーワードである「忘却」というテーマの重要性、またこうした一連の問いの、思想的そして市民的・個人的な、現代性、緊急性が浮き上がる。
対話相手として取り上げられる様々な他者の思想に加えて、本書で繰り広げられるリクールの問題提起も、その過程で取り上げられる問いは多様である。そして、それぞれの問いに深い考察が展開されている。こうした意味で、本書は、哲学者リクールの総括的書物なのであり、昨今の記憶、歴史の氾濫への批評・考察が現代思考の要の一つとして顕れることを示しているといえる。
La Mémoire, l’histoire, l’oubli,
Seuil, coll. « l’ordre philosophique »,
676p., 2000, 195F (29,73euros)