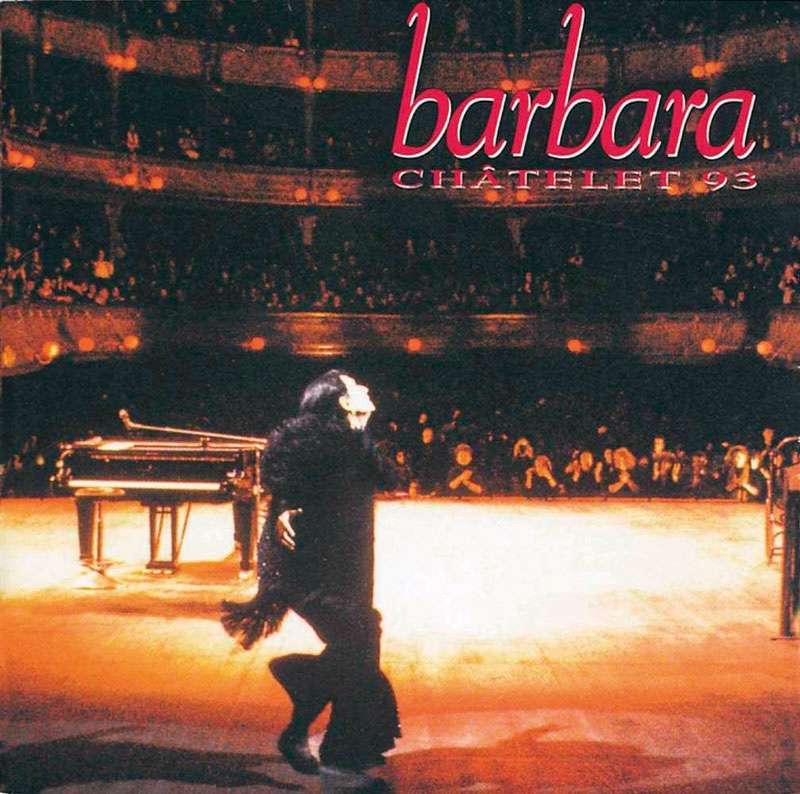悪の記憶、善の誘惑
prendre l’homme, dans son identité concrète et individuelle,comme fin ultime de son action,
le chérir et l’aimer
un individu (…) reste une, personne, infiniment fragile, infiniment
précieuse
過ぎ去った20世紀をどう理解するか。これは本書の出発点であるが、20世紀から21世紀へと通過した我々各自の問いでもある。著者トドロフは数十年来、
言語学者として知られている一方、本書以外にも数冊のエッセーを書いている。本書では、哲学的、歴史的「専門家」の視野からではなく、20世紀の一人の
「目撃者」、過ぎ去った時代を理解しようとする一人のエクリヴァンの視野から、20世紀の考察を展開している。
この問いはまず、20世紀の「事件」の総括から始まる。20世紀の中心的事件は新たなる悪の出現とされ、その悪とはファシズム、共産主義という二つの全
体主義である。この二つの体制が、民主主義とともに20世紀の三大体制をなし、この三者の衝突・再編成として20世紀の流れは理解される。
まずは共産主義が、ファシズムと民主主義を資本主義として括った時期、そして共産主義と民主主義が反ファシズムの戦線を張った時代、そして民主主義が共産主義とファシズムをいずれも全体主義とする時代。
こうした軸から見られるのは、戦争で代表される事件的歴史や人道的「人間性」の流れだけではない。そこで暴かれていくのは、ナチズムやスターリニズムの論理、如何にそれが残酷な手段を用いようとも、如何にそれが「非人間的」でありながらも、決して非論理的ではない全体主義の論理でもある。そして…、民主主義の論理、メカニズム、手段、政治の弱さ(この弱さが強さでもあるのは当然だが…)も浮き彫りにされていく。

この思想的総括及び問いかけは、次に、「記憶」の観点から論じられる。つまり、何を、如何に、記憶に留めるのか、過去の記憶をどう現在に生かすのか。「そこ(アウシュビッツ)で起こったことは理解されるべきではないかもしれない。というのも、理解することは正当化することだから」と語ったプリモ・レヴィに
対して、トドロフは、レヴィ自身も一生涯その理解に努めたことを記し、ルソーを引用した上で、「悪を理解することは、その再来を防ぐ手段を得ることである」と述べている。つまり、「全ての人間は « 潜在的に » 同じ悪を持ち得るものの、 »実際的には »
そうできない」のである。しかし、これが個々の事件の現実的理解の根本になるとはいえ、完全な理解はありえない。人間とは、悪の可能性を秘めていながらも、また理解への意思がありながらも、「完全」ではありえない、とトドロフは加える。
かえって、現代民主主義世界は、過去を祀ることや一般化してしまうことで、そして道徳的言説やメディアで覆っている。こうした過去・記憶の扱いには、それぞれ危険が伴う。本書から二つだけ例を引用しよう。フランス人にとって、1945年5月8日は終戦(-戦勝-)記念日であるが、アルジェリアのシェティ
フの大虐殺の日でもあることは記憶に留められない。1995年、広島の原爆投下から50年、日本は原爆を投下した軍機Enola
Gayの展示を拒否した。一方アメリカでは、12歳の子供が原爆が投下された時にもっていた弁当箱が展示されていることで、このエキスポジションの見学者
は少ないという。
こうした歴史的事件は、勝利者から、あるいは被害者から、というような善悪二元論から見られるべきではない。それは「悲劇」としかいえない。「善の不可能性、その結果が如何にせよ、涙と死しか生まない」と定義される「悲劇」でしかない。「悪」(その極端としてナチズム)が様々な形をとってあらわれた20世紀に、その記憶は「悲劇」としてのみ客観的、否、「人間的」視点—つまり人間の不完全さ、弱さ、そして、他者への涙、愛—から判断され、現在に留まるべきと示唆される。
こうした記憶の問題を通して、本書は最後に、20世紀という過去を現在に位置づけようと試みる。Nato、アムネスティ・インターナショナル、国境なき
医師団などの世界的機構の考察から、現代における過去の事件の判断の困難さ、その「道徳的正当性」(moralement correct)が考察される。コソボ、ルワンダで浮き彫りにされた世界的民主主義社会の曖昧さ、「国際化、普遍化」されていく世界の弱さ、「人類への罪」*を裁くことの虚構性が語られる。
壮大な問題を扱っており、かつ言語学者的な綿密さ、論理的言説をもって、この20世紀という問題をその細部にわたって論じ、問題の多様性も失っていない
本書。以上のような簡単な大枠の紹介だけでは、その聡明さ、明晰さは把握できないかも知れない。そして悲観的、シニカルに見られるかも知れない。
しかし、本書の特徴は、その明晰さにあるだけでなく、20世紀を例証する6人の人物像(V. Grossman, M. Buber-Neumann, D.Rousset, P. Levi, R. Gary, G.
Tillion)が、この20世紀の、そして21世紀への希望であるとされるヒューマニズム、「批評的ヒューマニズム」(humanisme critique)の例として挙げられていることにもある。
彼らの共通点は、ユダヤ人としての迫害を被ったことだけではない。人間が惨劇を実現できることを認めながらも(彼ら自身が実際に、悲劇的に、それを目の当たりにしたのであるから…)、彼らは、誰よりも、「人間を、その具体的かつ個人的アイデンティティにおいて受け入れ、人間を人間自身の行動の究極の目的とし、人間を愛おしみ、愛するものとする」者たちである。こうした先達が存在すること、彼らの記憶を我々が留められること、希望はそこにあるのだろう。
人とは「無限にかよわく、無限に尊い」のであり、これが、我々の各自が自身の中で、他者との関係において、悪の記憶を越える、そして越えることのできる、善の誘惑なのだろう。*crime contre l’humanité: ここでのl’humanitéとは、「人類」という「全体」ではなく、「人間性」という「個」にアクセントをおく意味で捉えられなければならないだろう。
Mémoire du mal, Tentation du bien – Enquête sur le siècle,
éd. Robert Laffont, 2000,
368p., 149F