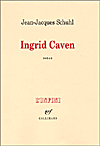●Jean-Jacques Schuhl « Ingrid Caven »
今年のゴンクール賞は、Ingrid Cavenというドイツ人歌手・女優を中心人物とした25年ぶりのJ.J.シュールの新作だ。
一言でいって、この小説は難しい。鍛錬されたフランス語、繊細かつ奇抜なエクリチュールは勿論、ドイツ語・英語なども織り込まれる。1943年のクリスマスに4歳半でヒットラーの兵士たちの前で歌い始め、40年後にはエルサレムで歌うことになる中心人物も「重たく」感じられる。そして彼女の人生が伝記的に年代順に語られるのでなく、時には細部の情景描写が前面に出されたり…と、言葉の面だけでなく物語構成の面でも読みづらい。しかし、この小説の面白さはこの難解さのみにあるのではない。
21世紀を間近にして、20世紀後半の50年を思考する者たちにとっては、例えば、中心人物であるドイツ人歌手と語り手である「ユグノー・ユダヤ人」との対話には考えさせられる。文学を愛する者にとっては、文学と音楽の関係、そして語りの問題などについて考えさせられる。さらに「セリーヌ研究者」は、数カ所セリーヌ的表現を見つけるだけでなく、『夜の果てへの旅』でのニューヨークの描写を見いだす。そして、こうした「真面目な」、「専門的な」面白さだけでなく、「軽い」面白さもある。「ポップアートの法王」ことウォーホルから、ケネディ夫人をへて、「横にジャンヌダルクがいる!」とドゴール将軍に真夜中に電話するマルローにいたるまで、多彩な登場人物がいること、また漫画『タンタン』と戯曲『ファウスト』が繋がってしまうことは、時には耐えられないくらいにシニックな語りを和らげるわけではないが、対称点を成し、この両極端間の揺れはリズミカルなエクリチュールと調和し、この作品独特の音楽を奏でる。
二十世紀の音楽的総括、これがこの作品の文学体験だ。(樫)