『 神のバルコニー(仮題) 』
Le Balcon de Dieu
ウジェーヌ・エボデ著 / Gallimard社
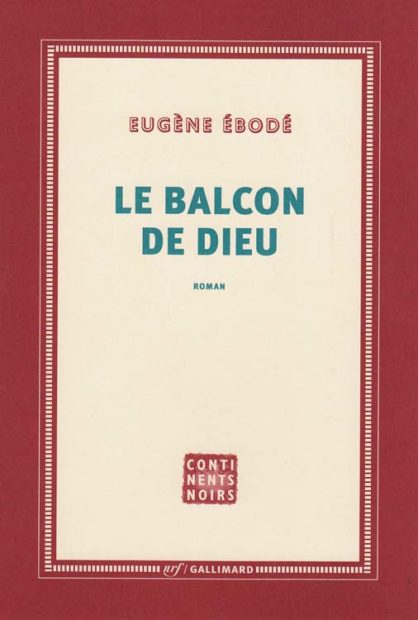
「神のバルコニー」。
アフリカ大陸の南東、モザンビークとマダガスカルに挟まれたインド洋に、マヨット島がある。フランスの統治から独立したコモロ諸島のなかで唯一本国への帰属を選択した地域で、最終的に2009年の国民投票によってフランスの101番目、つまり最期の「県」となった。
新婚旅行でモーリシャス島に旅立った南アフリカの若いカップル、ドノヴァンとメラニアは、飛行中に遭遇したサイクロンのためにフランスでも最貧困地域のこの島への滞在を余儀なくされる。しかしこの偶然は彼の国の偉大な元大統領マンデラを敬愛するドノヴァンに、一つの決断をさせる。荒廃し見捨てられた社会を目の当たりにした若者は、そこに移住して住民のために自らを役立てようと考えるのだ。こうしてその短い滞在からしばらく後、妻の強い反対も押し切り、幼い娘を連れ夫婦は島のある場所に居を定める。高い山地から海を見渡すことができるその地域は、マヨットの神話によれば、創造主「ムングー」が世界を生み出す際にそこから下界を眺めた場所として「神のバルコニー」と呼ばれていた。
貧困と移民。
英語教師として学校で働きはじめたドノヴァンは、改めてマヨット社会の惨状の深刻さを知る。貧困だけではない。そこに大きな問題として「不法」移民たちと地元住民との対立が加わるのだ。仏国立研究所の統計では、マヨットでは20万人の住民のうち41%は外国国籍で、その半数は不法状態にある。その多数は、より良い生活を目指して渡航するコモロ諸島の住民だが、彼らが手にするのは以前と同じかそれ以上に辛い暮らしだ。フランス国籍を我が子に与えるためにコモロの妊婦たちがマヨットに出産しに渡るのは有名な話だが、昨年はマヨットの上院議員から現地での出生地主義を例外的に限定する法改変案が提出され(マクロン大統領も賛意)、憲法違反ではないかと物議をかもした。
そんななかドノヴァンたち家族は大きな社会運動に巻き込まれるが、これも実際に起きた出来事が参照されている。マヨットでは2018年初頭から貧困と安全性の改善を求めて、デモや大規模なストライキ、バリケード封鎖による経済麻痺が起き、海外県担当大臣が出向く事態にまで発展した。この混乱は地元住民から移民・外国人への憎悪感情をも深めていったが、そんな危険な状況下でドノヴァンは、ある日海で溺れかけた娘を救った一人の少年を探していた。「神のバルコニー」で起きた土砂崩れで家族を失ったこの孤児に彼はとりわけ親身に接したが、ある時から行方知れずになっていたのである。だが必死の捜索も空しく、ドノヴァンは彼と再会できぬまま、行政との諍いをきっかけに島を強制退去させられる…。 「黄色いベスト」たちが街路に溢れかえるタイミングにこの本が出版されたことには、色々と考えさせられる。
フランス、マヨット、そして「アフリカ」。
マヨットの人々の怒りとは、貧困と不安を知りながら自分たちを見捨てた国家に対する怒りであり、この物語は「本土」の影に隠れた人々の意志を、再び目に見えるものにするのである。とはいえそれが全てでもない。むしろ話の核心は、所属する国家からも人々のルーツであるアフリカからも切り離された孤児のようなマヨットの悲惨を、ドノヴァンが「アフリカ人」としてどう受け止めるかという問いにある。だが白人で英語を話す彼は周囲から決してそのようには見られない。マヨットの人々にとっての「アフリカ」とは、コモロの人々、彼らがもたらす災厄、否定すべきものでしかないからだ。ところがドノヴァンにとっては、国家を越えた責任と連帯を生む肯定的な意味を持っている。もっとも、彼の愚直な人道主義は失敗に終わるのだが…。しかしこの愚直さまでも失ったとき、人は真の意味での貧しさに陥るのではないだろうか。(須)

Francesca Mantovani
ウジェーヌ・エボデ
1962年、カメルーンの都市ドゥアラに生まれる。若い頃はナショナルチームに選出される程の優れたサッカー選手だった。82年渡仏、学業を修め、40歳で初の自伝的小説『伝達』を発表。







