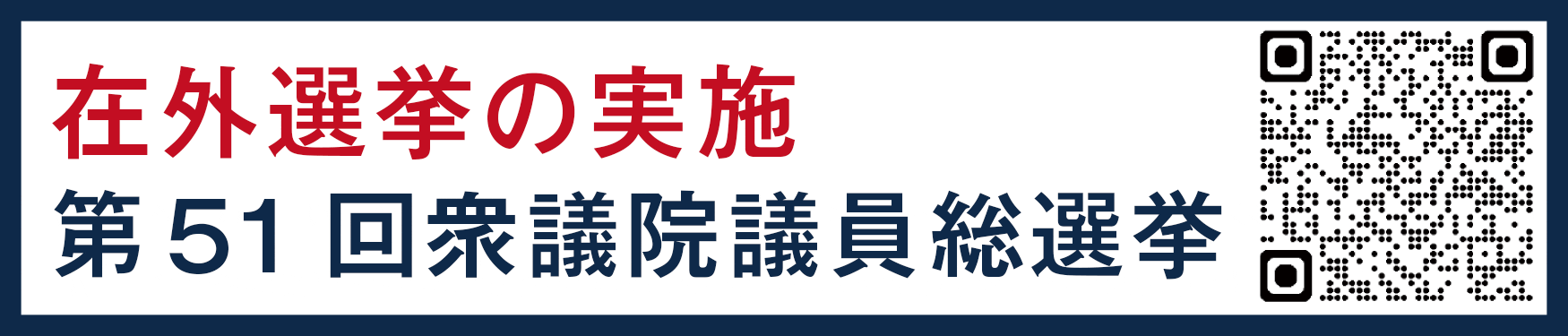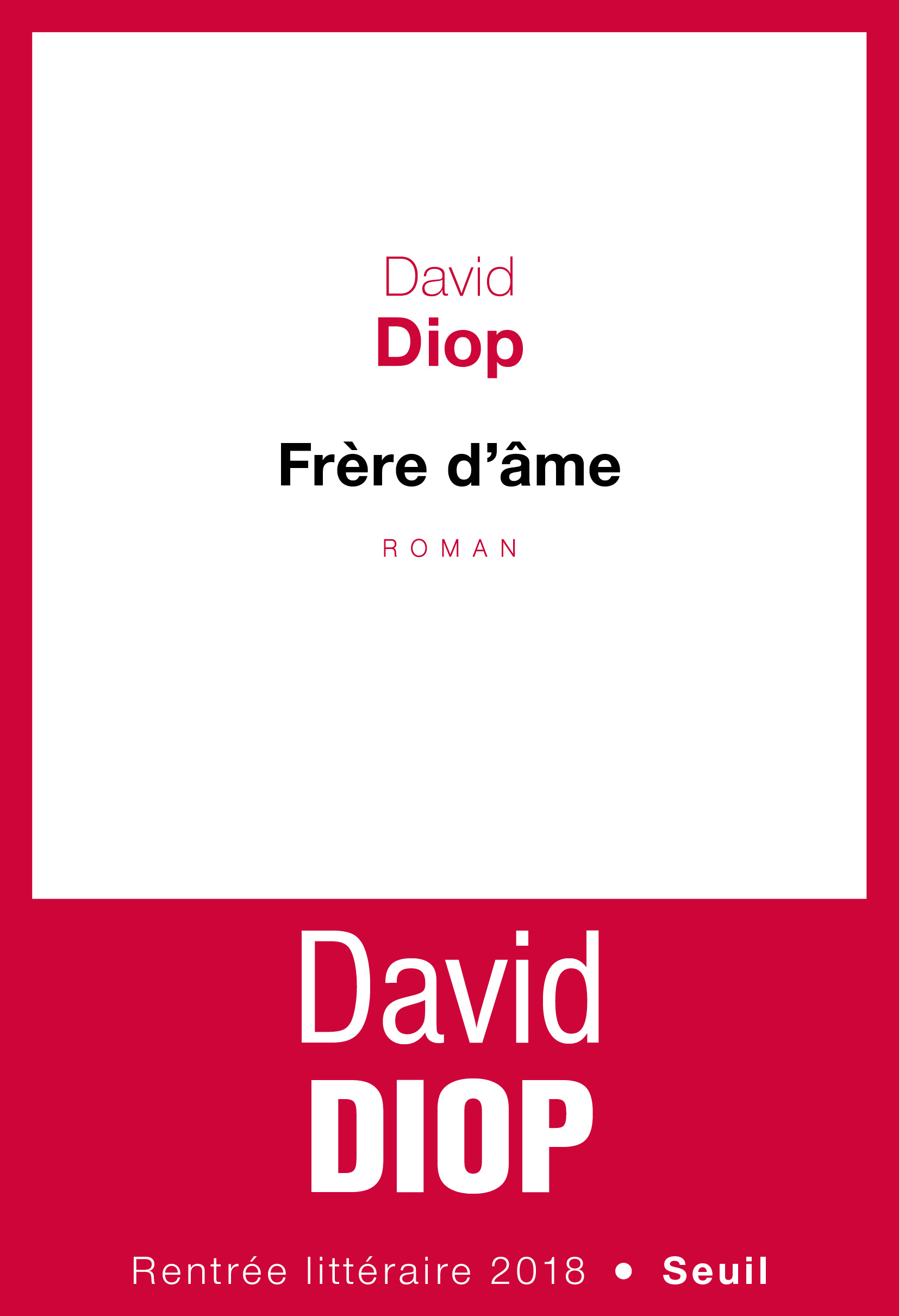『 魂の友(仮題) 』
Frère d’âme
ダヴィド・ディオプ著 / Edition Seuil刊
世界大戦と「セネガル狙撃兵」。
二つの世界大戦中、フランスのために戦ったアフリカの人々がいた。彼らの数は1914〜18年の期間だけで23万人にも及び、そのうち13万4000人の「セネガル狙撃兵」が戦地に送られたとされる。海向こうの植民地から、彼らのものではない戦争へと駆り出され、ある者たちは身体や精神に傷を負い、また別な者たちは歴史に名を残すことなく命を落とした。この物語の主人公、アルファ・ンディアイや彼の親友マデンバ・ディオプもまたそのなかの一人だ。
二人はセネガル北西部、ガンジョルの村で幼少期からともに育ち固い絆で結ばれた仲だった。ある日、戦場でマデンバは深い傷を負い、そのままアルファの目の前で死んでしまうのだが、そのとき彼は親友の最後の願いを叶えてあげることができなかった。耐えがたい痛みに、マデンバは「犠牲の羊のように」自分の喉を掻き切って殺してくれるよう嘆願したが、彼はそれを拒絶する。
戦場の狂気。
アルファは、無二の友を最後の苦しみから救えなかったという自責の念にかられる。「知ってるさ、わかってるんだ、そうするべきじゃなかったんだ…」。幾たびとなく繰り返されるこのフレーズは、口にされる度にアルファの生きる時間をマデンバの死の場面へと巻き戻す。また同時にそれは、アルファの思考にリズムを与え、さらに、彼のなかに一種の「狂気」を生み出し、そして加速させてゆく。というのも、友を失い一人となったアルファは豹変するからである。
それは復讐心からか?それとも友の許しを乞うためか?アルファは友の果たされない願いを清算するかのように、ドイツ兵の喉を切り裂き、はらわたをえぐり出す。彼は夜になるまで機会を待ち、そして狙い定めた一人だけにそれを実行するのだ。しかもそこに「戦利品」まで加えて…。彼は毎回、自分が殺害した兵士の銃と、それを持っていた手首を切りとり、戦友たちの待つ塹壕まで持ち帰ったのである。初めのうちは仲間たちから英雄扱いされたものの、回を重ねるごとに反応が変わり始め、そして「戦利品」が7つになったとき、アルファは仲間たちからも恐れられるようになる。それは「文明人」の戦争においてあまりに「野蛮」とみなされたのだ。こうして、隊長でさえも持て余す厄介な存在となったアルファは、後方へと退き休暇を取るように命じられる。彼は完全に孤独となる。
「野蛮」とは何か?
しかし戦争という極限状態のなかで、何が「野蛮」で何がそうでないか、誰にわかるのだろう?命令に背いた「裏切り者」たちを敵砲兵の砲弾の餌食にし、炸裂した血と脳みその雨を降らせたフランス人隊長は、いかなる点でこのセネガル人兵士よりも「文明人」であるのか?
アルファはこの疑問に哲学的な省察を行っている。「隊長殿のフランスは俺たちが野蛮人になるのを望んでるのさ、それが都合のいい時にはな。(…)彼らと俺の唯一の違い、それは俺が熟慮によって野蛮になったということだ。彼らは地中から出たときにだけコメディを演じるが、俺は彼らと一緒のとき、護ってくれるこの塹壕のなかでだけコメディを演じるのさ。仲間内で、俺は笑い、調子外れに歌いさえしたが、彼らは俺を尊敬していたんだ」。
皮肉にも、この演技による残虐さの反復は結局、彼の精神を蝕み、破壊してしまう。休暇が与えた時間のなかでセネガルの記憶を追想しながら、いつの間にかアルファ自身の魂は消え失せ、彼の体は失われた友の魂へと譲り渡されてしまうのだ。この究極的な贈与によって、彼らは文字通り「魂の友」となったのである…。一次大戦中に死亡した「セネガル狙撃兵」はおよそ3万1000人と言われる。(須)

© Hermance Triay
ダヴィド・ディオプ
1966年パリに生まれ、セネガルで育つ。現在はポー大学で18世紀仏文学を教えている。今回で小説は2作目。同姓同名の著名なセネガル人詩人がいるが、別人である。