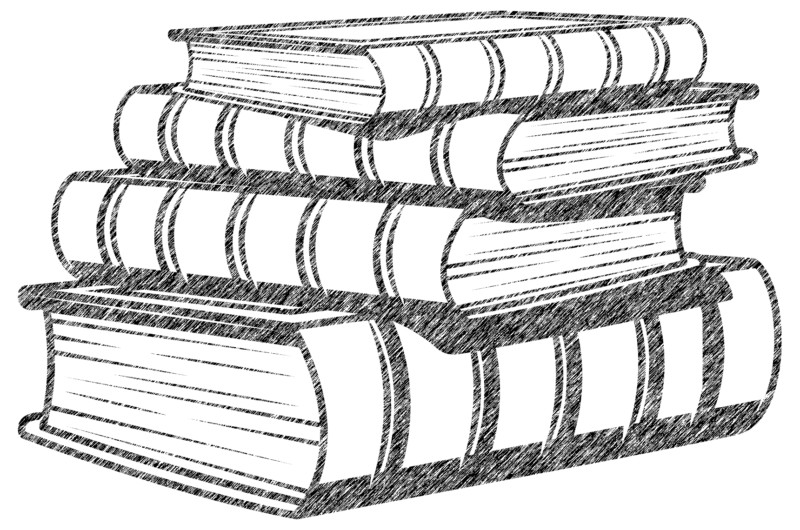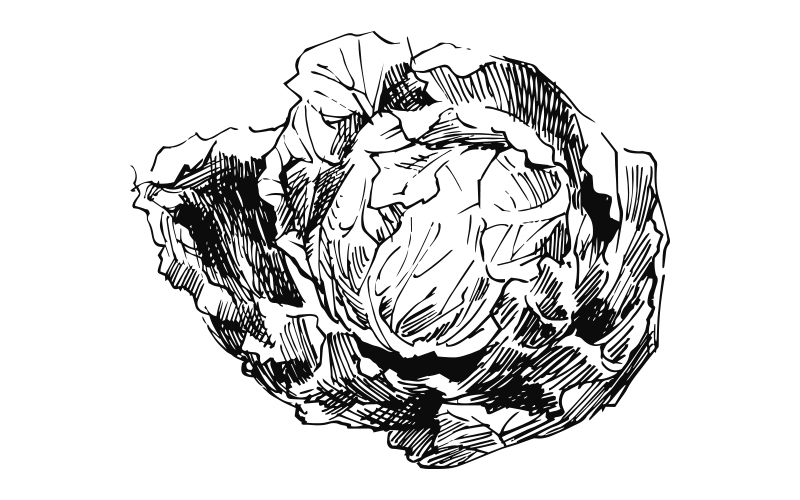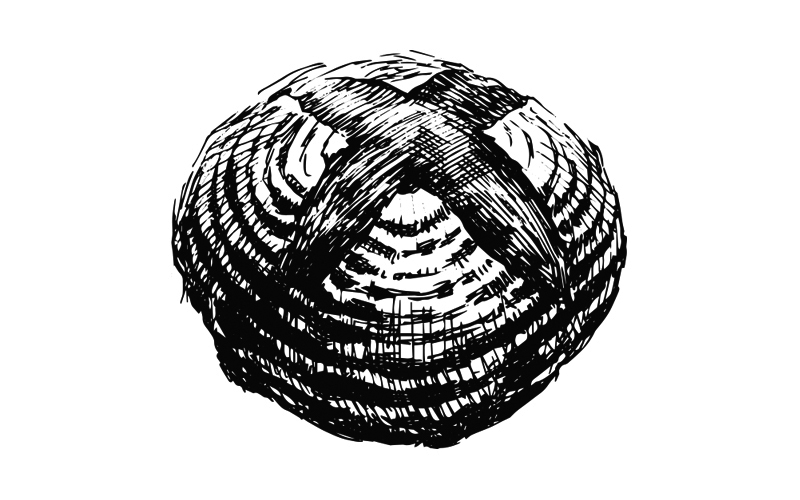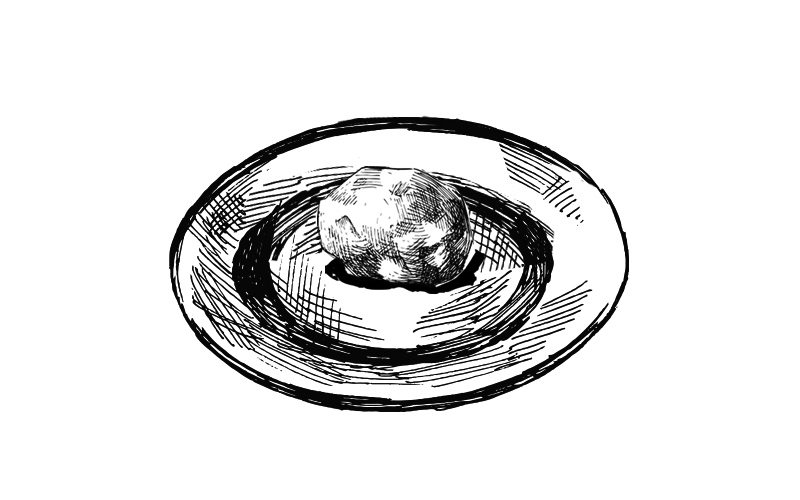ルネッサンスを生きた哲人モンテーニュは、読書や執筆の時間を愛しながらも、生身の人間との交際を何よりも大切にしていた。「ほかに何もする気になれないほどの倦怠にとりつかれたときでないと本に没頭しない」(原二郎訳)と明言しているほどだ。
そもそも、書斎のある塔にこもって『エセー』を書くことになった理由のひとつは、最愛の友であるラ・ボエシーが亡くなったことだった。ラ・ボエシーについての記述をたどれば、その友情がどれだけ尊いものだったのか、また、それだけに、友を亡くした時の喪失感はいかほどだったのかを想像せずにはいられない。手紙を書く相手がいたならば、モンテーニュが『エセー』を書くことはなかった。「われわれが友を失ったときに、『われわれはおたがいの間に何も言い忘れたことがなかった。われわれは完全な交際をした』という自覚をもつこと以上に快い慰めはないからです」という一節がある。ラ・ボエシーに言い忘れたこと、言えなかったこと、もしくは繰り返して語り合いたかったことなどを『エセー』として綴ることで、モンテーニュは慰めを得ていたのかもしれない。
ところで、モンテーニュにかかると、生活のすべてが研究の対象になる。「われわれの目前に現れるあらゆるものが恰好の書物として役に立ちます。給仕の悪意、従僕の愚鈍、食卓での談話、そうしたものがすべて新しい材料となるのです」。
だからこそ、「何を食べるかということよりも誰と食べるかということを重視すべき」だし、「皆と一緒に食事をすることからくる楽しみほどうまいご馳走はないし、またそれほど食欲をそそるソースもない」ということにもなる。
ところで、食卓を豊かにするためには、もうひとつ大事な要素があるようだ。賢人は説く。「他の時間を有効に使ったという自覚は、食事の正しくおいしい薬味である」。(さ)