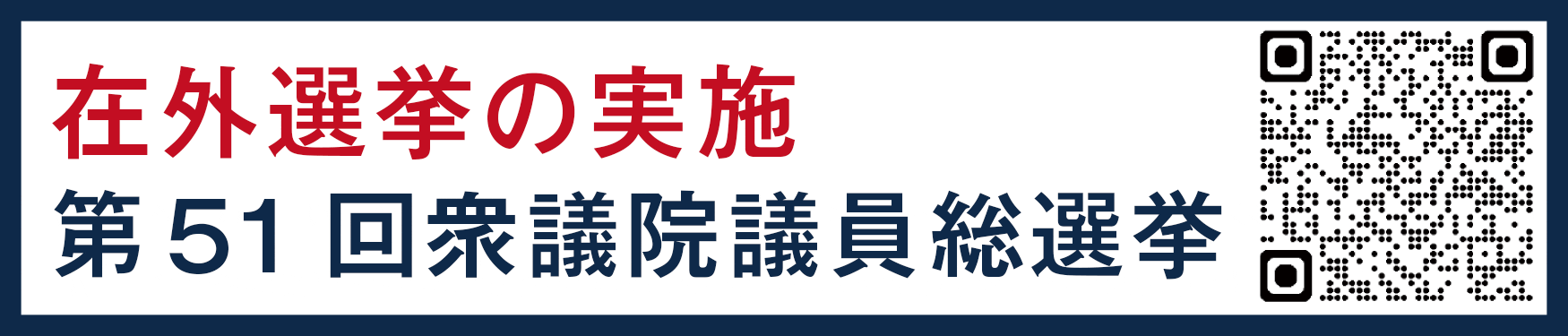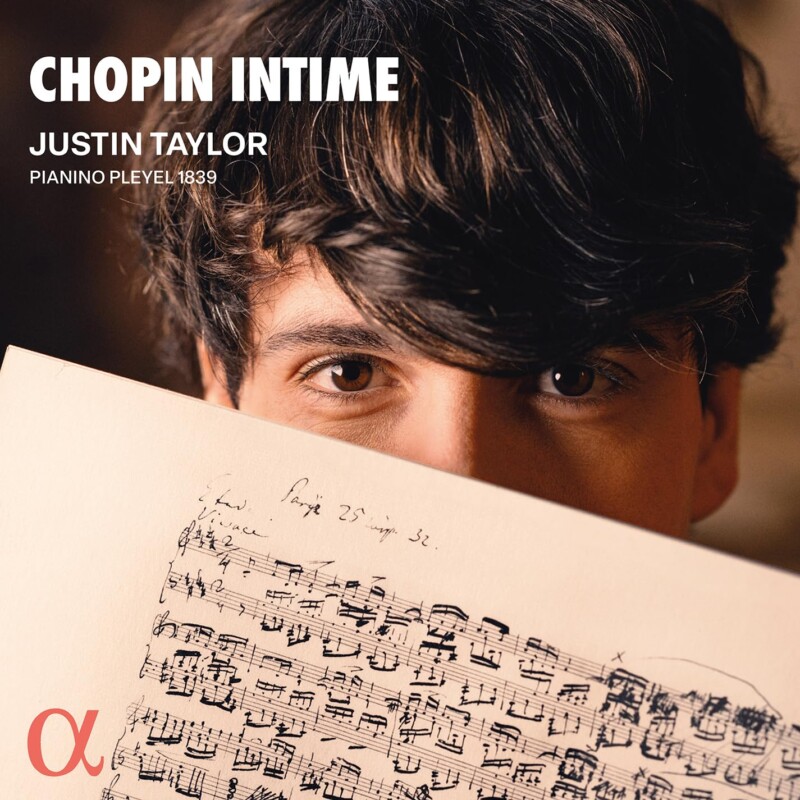時は流れ、千年はマチルドと結ばれ東京で教授職に就き日本で年輪を重ねていき、クレマンスは短い全盛期の後、家庭に入り声楽界から忘れ去られる。病身の妻を家に残し、29年前の夢に会いに行った千年は、29年前と同じオペラ座裏のビストロで、29年前と同じように元歌姫と夜更けまで熱く語り合うのである。
小説に現れる数々の映画的リファレンス(コルノー『めぐり逢う朝』、黒澤『生きる』、カウリスマキ『ル・アーヴルの靴磨き』…)の中で最も重要と思われるヒッチコックの 「めまい」は、キム・ノヴァックが瓜二つの被害者の女と加害者の女の二役を演じる(実は二人は同一人物)ものだが、後者と恋に落ちたジェームズ・スチュアート演ずる元刑事が次第に死んだ前者に惹かれていく。この不在者への愛の例こそが、クレマンスとの成就しない恋の鍵であるように千年は説明する。
しかし小説の最大のリファレンスは歌劇『フィガロの結婚』であり、封建的貴族社会を背景に風刺と笑いのうちに下僕と侍女が伯爵の好色強権を覆して大団円の結婚を迎えるのだが、身分階級の異なる6者による六重唱の闘争的ながら調和的な絡み合いを侍女スザンナが誰よりもリードする時、モーツァルトの政治的革命的意図も明白になる。これを民主主義と呼べないか。音楽家となる代わりに、千年は楽器を習得するようにフランス語をマスターしたと言う。オーケストラの中では一つの作品を前にしてあらゆる演奏者は平等である。そして演奏者は他の楽器の音を聞かなければならない。オーケストラは人生と民主主義の学校である — このような作者のヴィジョンから見ると、今日の日本のあらゆる声を窒息させて暴走する体制が耐え難いものとなる。
『千年の愛』はフランス語小説であり、楽器のようにフランス語を奏でる作者による恋愛と音楽と政治と人生の書である。日仏バイリンガルの方なら、この千年氏にフランス語を内在化するということの徳を改めて教えられよう。和訳本はすぐに出ないかもしれないがそれでいい。これはこちら側の小説だ。