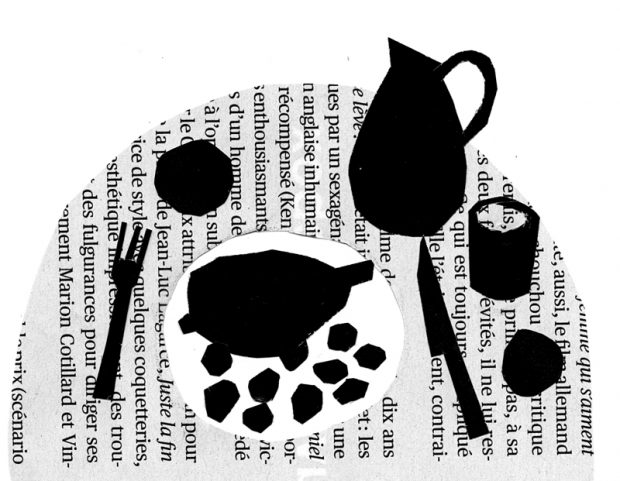 モーパッサンの小説『女の一生』(1883年)は、リアリズム文学の傑作として知られている。その小説に多分に影響を与えたのが、モーパッサンの師匠だったフロベールの『ボヴァリー夫人』(1857年)。ともにノルマンディー地方の出身だった両作家は、その地方に暮らす人々の暮らしをつぶさに描くことで、その心理までも浮き彫りにした。
モーパッサンの小説『女の一生』(1883年)は、リアリズム文学の傑作として知られている。その小説に多分に影響を与えたのが、モーパッサンの師匠だったフロベールの『ボヴァリー夫人』(1857年)。ともにノルマンディー地方の出身だった両作家は、その地方に暮らす人々の暮らしをつぶさに描くことで、その心理までも浮き彫りにした。
暮らしを描くにあたって、フロベールは登場人物たちの食習慣を事細かに記した。例えば、主人公のエマ・ボヴァリーの父親で、農場主のルオー老人。「こくのある林檎酒、血のしたたる羊の股肉(ももにく) 、念入りにつくったグロリア(ブランデー入りのコーヒー)が好きだ。台所で暖炉にむかって舞台でのようにすっかり料理をならべてもってきた小テーブルでひとり食事をした」。(生島遼一訳)
豊かな田園風景の中に建つ木造の家、召使いによって清潔に整えられた室内、小鳥のさえずりや風の音くらいしか聞こえてこない静寂な台所で、ひとり好物に舌鼓を打つ初老の男性の姿が目に浮かぶ。百姓とはいえ、農作業そのものよりも商売の取り引きを得意とするルオー老人。そこには、純朴な農夫とはタイプの異なる、抜け目のない商売人の顔が見え隠れする。
そんなルオー老人は、娘のエマを医者のシャルルのもとに嫁がせることに。将来の婿のことを「少々貧相」だと思いながら、「おそらく持参金のことでとやかくいいそうでもない」ということも手伝って、ふたりの結婚を積極的に応援するのだった。
時は19世紀。娘が年頃になると「持参金」をたずさえて嫁ぎ、その持参金は夫の所有する財産になった。「恋愛結婚」という概念さえもなかった時代だった。(さ)






