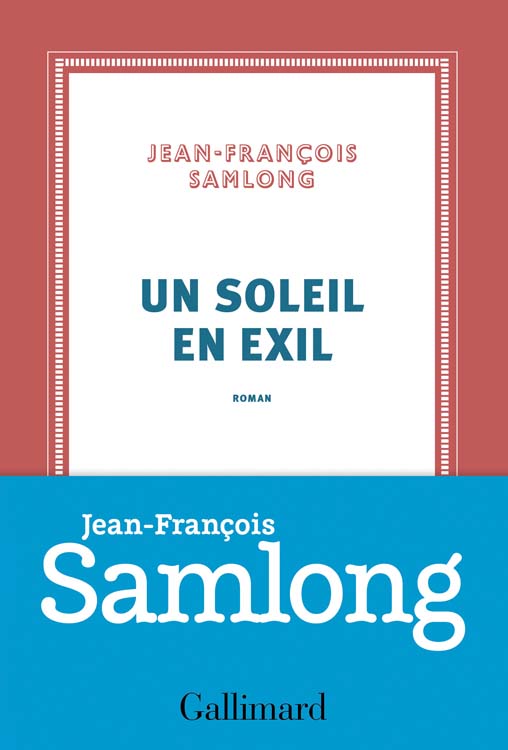『 流刑の太陽(仮題) 』
UN SOLEIL EN EXIL
ジャン=フランソワ・サムロン著
Gallimard刊
子供たちの強制移住。
1962年から1984年の間、仏領海外県レユニオンからフランス本土へと、二千人を超える子供たちが集団的に移住させられた記録がある。その移住先は中央部のクルーズ県をはじめとする田舎であり、この集団移住は、当時レユニオンから選出された国会議員であったミシェル・ドブレによって推進された、過疎地域の人口増加政策によるものだった。子供たちを親や兄妹から強制的に引きはがすことを「合法的に」可能にしたこの政策は、当然ながら当事者たちの人生を大きく狂わせた。故郷を失った悲しみや移住先での悲惨な境遇から、なかには精神に病を抱えたり、自殺した子供たちさえいる。この歴史は、国家の一大スキャンダルとしてレユニオンの人々にはよく知られているが、当時のフランスのメディアではほとんど報じられることさえなかったという。フランスの国民議会がその政策の「道義的責任」を認めたのでさえ2014年2月、つい最近のことである。
姉の捜索と弟の死。
物語の主人公エヴァは16歳のときに、二人の弟・トニーとマニュエルとともにクルーズ県へと移送される。到着するやいなや姉弟は離ればなれにされ、エヴァはある婦人の屋敷で家事手伝いとして働くことになり、二人の弟は行方知れずとなる。彼女が未成年であることを理由に、役人たちは彼女に弟たちの受け入れ先を知らせなかったのだ。しかしエヴァは、父は牢獄、母は病身で、レユニオンにいた頃からすでに一家の支柱として振る舞わねばならなかった。そんな彼女にとって、弟たちは彼女が護らねばならない息子のような存在でもある。彼女は弟たちを懸命に探す。幸いにも彼女には協力者たちが現れる。雇い主である婦人やその周囲の人々の理解のもと、彼女は親切な労働視察官と共に、南へと出発する。わずかな手がかりを頼りに、二人は弟たちの行方を突き止める。だがそこに待ち受けていたのは、レユニオンの子供たちが生きた過酷な現実だった。
彼らがトニーをある農家の納屋で見つけたとき、彼はすでに屍となっていた。トニーは自殺したのだ。農家は彼ら子供たちの主要な受け入れ先の一つだったが、そこでは、ろくな食事も与えられず、早朝から日暮れまで働かされる奴隷のようなものだった。ここで悲惨なのは、彼のように納屋や家畜小屋に押し込められ、動物のように扱われる生活が、レユニオンの子供たちにとって決して例外ではなかったことである…。
「デポルタシオン」の歴史。
こうした背景には人種の問題がある。当時のクルーズでは「黒人」はきわめて珍しい存在であり、ましてやそのような存在が自分たちの住む場所に突如として集団で現れたのだから、驚きと拒絶が起きたとしてもなんら不思議ではない。それは逆の立場からも言えることで、思春期の子供たちがいきなり言語(彼らはクレオール語を話した)も文化も異なる場所に置き去りにされたときの衝撃は、もはや私たちの想像を絶するものといえるだろう。
ところで、この集団移住には「デポルタシオン」という言葉が使われるが、多くのフランス人がこの言葉でまず思い浮かべるのは、第二次大戦中にナチの強制収容所へと送られた人々だろう。実は物語の中で、エヴァと雇い主の婦人の対話を通じて、この二つの「デポルタシオン」の歴史が交錯するような場面が描かれている。もちろん二つの出来事の単純な比較はできない。けれど、家族や故郷を失う悲しみは誰にも共通するものだ。だからこそ、この二つの歴史を並べることで作者が願っているのは、子供たちが受けた苦痛を、他人事としてではなく、人種を越えたフランスの歴史として見てほしいということではなかろうか。(須)
 [著者]
[著者]
ジャン=フランソワ・サムロン
1949年レユニオン島サント=マリーに生まれる。1982年からレユニオン社会における暴力を問う作品を継続的に発表し続ける。本作で小説は13作目。