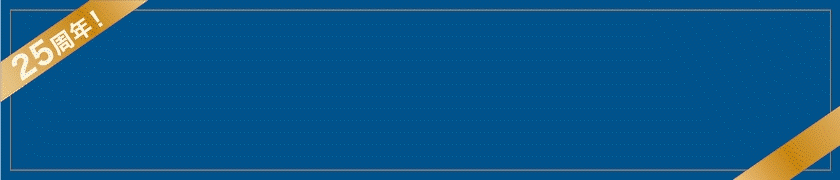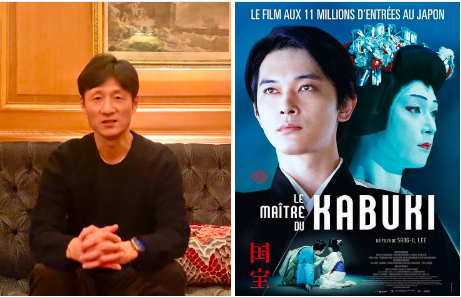第二次大戦前にF・ラング(『メトロポリス』)やG・W・パブスト(『パンドラの箱』)、G・W・ムルナウ(『吸血鬼ノスフェラトゥ』)などの巨匠を生んだドイツ映画界がヒトラー政権、東西分裂後を経て、再び活気を取り戻すのは、1960年代末期のこと。ニュー・ジャーマン・シネマという新しい流れは、W・ヘルツォーク(『アギーレ/神の怒り』)、R・W・ファズビンダー(『マリア・ブラウンの結婚』)、V・シュレンドルフ(『ブリキの太鼓』)、W・ヴェンダース(『都会のアリス』)などの作家を産出した。
その後、1980年代以降は? ベルリン映画祭は相変わらず存在し、独自の活動を続けるヴェンダースやヘルツォークなどがいたとはいえ、ドイツ映画界は世界からとりのこされていた感があった。それが、1998年にT・テイクヴァが発表した『ラン・ローラ・ラン』あたりから再びドイツ映画界は活性化し始め、そして2003年W・ベッカーの『グッバイ・レーニン!』で、東西統合後初めてドイツ映画は世界から注目を得る。とはいえ毎年フランスで公開されるドイツ映画は5本から10本にしか満たない。ただ去年から今年にかけ運良く多くの作家にめぐり合う機会に恵まれた。
まずは昨年ベルリン映画祭で金の熊賞を獲得したF・アキン(『Head on 壁に向かって』)、フランスのプレスがジャーマン・ヌーヴェル・ヴァーグと取り上げたH・ウィンクラー(『Voyage Scolaire』)、J・クルーガー(『En route』)、そしてA・シャヌレク(『Marseille』)のトリオなど、アキンを除けば商業ベースには乗らない作品を発表しているけれど、いずれも30-40歳代と若く、ドイツ映画の将来を背負う作家として育っていく素養を持っている。今劇場で見られるドイツ映画では、先に挙げたアキンの『Crossing the bridge』がおすすめ。トルコからの移民二世として生まれた監督は、『Head On』で音楽を担当したベース奏者と共に、イスタンブールで活躍するミュージシャンたちを追う。東西の文化が独特な融合を見せ活気を見せるイスタンブールという街、そしてそこに流れる音楽の多様性、さらにはやはりドイツに生まれながら自分のルーツに魅せられるアキンの熱い思いが伝わってくる。
フランスではCNC(国立映画センター)が国の映画製作を援助したり監督する機関として存在するように、ドイツにもミュンヘンを拠点にGerman Filmsという国営組織が存在する。このGerman Filmsは、毎年10月にパリ6区にある映画館Arlequinでドイツ映画祭Festival du cin士a allemand a Paris(右欄参照)を主催している。今年の開催期は10月12日から18日まで、ドイツ映画の新しい作家に出会ういいチャンスだろう。また、10月にはヴェンダースの新作『Don’t come knocking』と長編アニメ作品『Laura Stern』の公開が控えているのも楽しみだ。(海)

Crossing the bridge
映画祭開催10周年を記念して、10月12日~18日の7日間、映画監督や批評家、歴史家らによって選ばれたドイツ映画ベスト100のうちからさらに〈世紀の15大フィルム〉として厳選した作品を紹介。映画の創成期に深く刻まれるスクラダノフスキー兄弟による短編『Wintergarden-programm』から、新しいジェネレーションを代表するファティ・アキンの『Head On』までを網羅する興味深いプラグラム。
WINTERGARTENPROGRAMM
1895年、無声、白黒、7分、Skladanowsky監督
LES MYST餝ES D’UN SALON DE COIFFURE
1922/1923年、無声、白黒、25分、Erich Engel & Bertolt Brecht & Karl Valentin監督
LES AVENTURES DU PRINCE AHMED
「アハメッド王子の冒険」
1923/26年、白黒 / カラー、65分、Lotte Reiniger監督
LA RUE SANS JOIE「Joyless Street」
1925年、無声、白黒、96分、Georg Wilhelm Pabst監督
M LE MAUDIT「M」
1931年、白黒、110分、Fritz Lang監督
LES ASSASSINS SONT PARMI NOUS
「殺人者はわれわれの中にいる」
1946年、白黒、100分、Wolfgang Staudte監督
LES SS FRAPPENT LA NUIT
1957年、白黒、100分、Robert Siodmak監督
TRACE DE PIERRES
1966年、白黒、139分、Frank Beyer監督
J’AVAIS DIX-NEUF ANS
「その時私は19才だった」
1967年、白黒、120 分、Konrad Wolf監督
ALLEMAGNE EN AUTOMNE
1977/78年、123分、R.W.Fassibinder監督他
L’AMI AMERICAIN「アメリカの友人」
1977年、63分、Wim Wenders監督
LE TAMBOUR「ブリキの太鼓」
1979年、145分、Volker Schlondorff監督
LES ANNEES DE PLOMB「鉛の時代」
1981年、110分、Margarethe von Trotta監督
MALINA「マリーナ」
1990年、125分、Werner Schroeter監督
HEAD ON「壁に向かって」
2003年、121分、Fatih Akin監督
上映会場 : Cinema L’Arlequin
76 rue de Rennes – 6e – 01.4544.2880
10月12日~18日
入場料 : 5 euros
M。 Saint-Sulpice
M。 Rennes/Sevres-Babylone
●TELEVISION
ARTE、ドイツとフランスの共同テレビ局
独仏共同資本の国営放送として1991年に出発したテレビ局ARTEでは、主に文化、教養番組と映画作品を放送している。フランス側の親会社であるARTE FRANCEの子会社としてARTE FRANCE CINEMAが存在する。
ここでは年に約20本の映画作家たちのドキュメンタリー&フィクション製作を行い、年間に費やされる予算は平均700万ユーロを超える。毎週月水木日曜日に放送される映画作品の一部はARTEが製作したもの。資金を出す代わりに製作前に放送権を獲得する、日本では珍しいけれどフランスまたはヨーロッパではほとんどのテレビ局がこのような<青田買い>方式で映画製作を援助している。
またドイツのARTE DEU-TSCHLAND 側では、ドキュメンタリー番組の製作や、DVDや書籍の出版に力を入れている。(海)
ARTEホームページ:
http://www.arte-tv.com