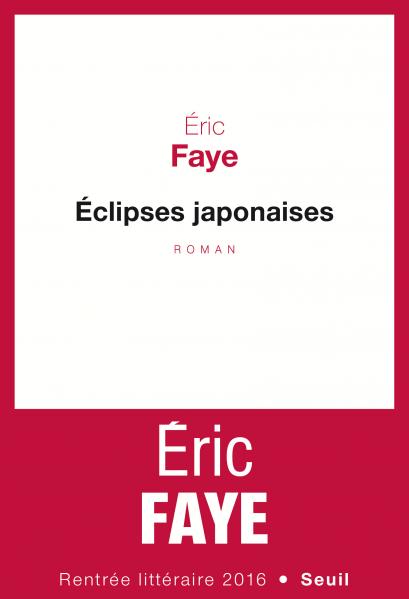「小説も、記事も、的確な言葉を使った表現が強いられる点では同じ」と言うエリック・ファーユさん。1991年から、一年に一冊のペースで著書を出版する現代フランス文学の旗手は、ロイター通信で速報を書く記者でもある。
「小説も、記事も、的確な言葉を使った表現が強いられる点では同じ」と言うエリック・ファーユさん。1991年から、一年に一冊のペースで著書を出版する現代フランス文学の旗手は、ロイター通信で速報を書く記者でもある。
10年前「未知の国だから、行ってみた」日本。そこで〈もっと知りたく、行きたくなる日本の罠〉にかかってしまった。2010年に小説『Nagasaki長崎』でアカデミー・フランセーズ賞を受賞、2012年、夏から秋にかけて日本に滞在し、日々の印象を綴った『Malgré Fukushima みどりの国の滞在日記』、そして今秋『Eclipses Japonaisesエクリプス』を出版。日本が舞台の著書は全作品の1割にすぎないが、今では日仏両国で「日本好きのフランス人作家」として知られる。なぜ日本が好き?と聞かれても「はっきり答えられないが、居心地がよい」と言い、「陰と、光らないものに惹かれるからかもしれない」、と滞在記に記している。
新作『エクリプス』は、北朝鮮による日本人拉致事件を小説化したもの。この事件を通信社の仕事で知り「20・21世紀の悲劇の主人公は、オレステスでもオイディプスでもなく、歴史と政治によって運命を変えられた普通の人々。拉致問題には現代の悲劇が凝縮されている」と感じ、4カ月間、韓国と日本で取材。日本海沿岸を旅して風景をノートしたり、佐渡島でジェンキンスさん(40年近く北朝鮮から出られなかった元在韓米軍軍人)や、事情に詳しい記者に会い、元工作員の金賢姫など関係者の証言を読んだ。一冊の本を書くにはたくさん過ぎるほどの情報を蓄積してフランスに戻り、事実関係だけでは手が届かない、心のひだを、小説家の感性と想像力で書き上げた。
独裁国家の陰謀に巻き込まれ、過去も素性も抹消された人や、その家族。取材するうちに身近に感じるようになった登場人物の日常に、極力近い作品を書きたかったという。行方不明の人たちが新聞記者の調査によって拉致被害者だと明らかになる過程や、工作員に仕立て上げられ爆破事件を起こす若い女性の心境、日本の日常から突如切り離され工作員養成学校に放り込まれ、日本語や子守唄を教える少女の孤独に迫った。青森出身の考古学者だけは架空の人物だ。在日韓国人の家庭に生まれ、革命により理想の社会を実現したと信じる北朝鮮に行くことを夢見ていた少年が、中年を過ぎて拉致される設定だ。
夕方、日本の住宅街を歩いていると聞こえてくる大根を切る包丁の音など、日常生活の情景があちらこちらで小説を彩る。「前から好きだった日本映画を観たり(黒沢清と成瀬巳喜男がお気に入り)日韓の友人に、日本人・韓国人らしさについて質問したり、事件について調べたりしているうちに、日本が自分に浸透してきて、日本人の登場人物の語り口も想像できるようになった」という。そうトリックを明かされても、あまりにも日本の描写はさりげなく自然で、小説家の頭というのはつくづく不思議なものだと思わされる。
旅が好きなファーユさん、次作はチベットが舞台なのだそうだ。(集)
『Eclipses japonaises』Seuil社刊。
松田浩則訳『エクリプス』水声社刊は12/7発売。