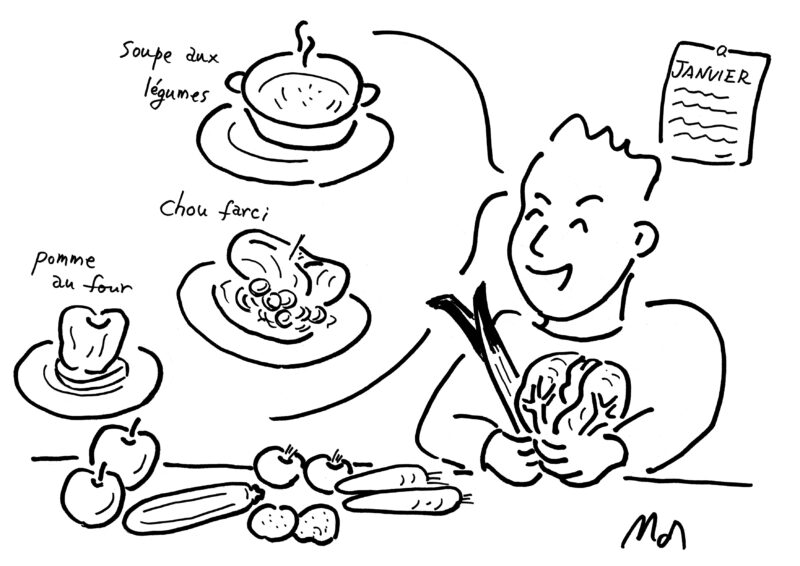フランス人にとって、ショコラ、つまりチョコレートはただのデザートではない。
バレンタインやパック(復活祭)、ノエルに欠かせない祝祭の彩りをまとうものであると同時に、ごく気軽に日常的に口にする食品でもある。
朝食にチョコレートベースのクリームをバゲットに塗りつけたり、パン・オ・ショコラをほおばったり。カフェでコーヒーを頼むと、一口サイズの薄い四角の板チョコがそえられていることもある。パティシエにとっては、バターや卵などと同様に、クリームや生地を作るうえでの基本的な材料のひとつ。もちろん、オペラやガトー・オ・ショコラなど、ショコラを主役にしたデザートも数多い。ワインやお茶について、「ショコラのような香りがする」などと、得意げに説明されているのを見かけることもあるし、布や皮などの色合いを「茶色」ではなく「ショコラ」と呼んだりもする。
そんな、皆に愛されているショコラのもとになるカカオの木の歴史は、2500年ほど前の中南米にさかのぼるといわれている。当時は、カカオベースの飲料には香辛料がたっぷり入っていた。現代のようにポリフェノール効果がうたわれていたはずもないけれど、健康を促進するものとして珍重され、カカオ豆は貨幣代わりに利用されていたという。
私たちが飲むような砂糖入りの甘いショコラ・ショーは、16世紀にスペイン人が「新大陸」を発見した頃のこと。そんなショコラは聖職者や貴族によってヨーロッパに広まり、17世紀以降はフランス宮廷でもずいぶんもてはやされた。一般市民がショコラを口にしはじめるのは、18世紀末のフランス革命後になる。フランス革命は、味の革命でもあったのだ。
フランスを代表する作家の中にもショコラに目がない人は多い。アナトール・フランスの『小さなピエール』には優雅なショコラ店の話が、プルーストの『失われた時を求めて』には料理女フランソワーズのつくるチョコレートクリームの話が登場する。物語の中で丁寧に語られているショコラの思い出は、読む者に幼少期の幸福感を思い出させてくれる。実生活でもショコラが大好物だったモーパッサンの短編「Ce cochon de Morin」には、いかにもこの作家らしい、ちょっと官能的なショコラ・ショーが登場する。
ちょうど、あたたかい飲み物が恋しい季節。しっかり暖房のきいたカフェのテラスに陣取って、読書をしながらショコラ・ショーを飲みたい気分です。(さ)