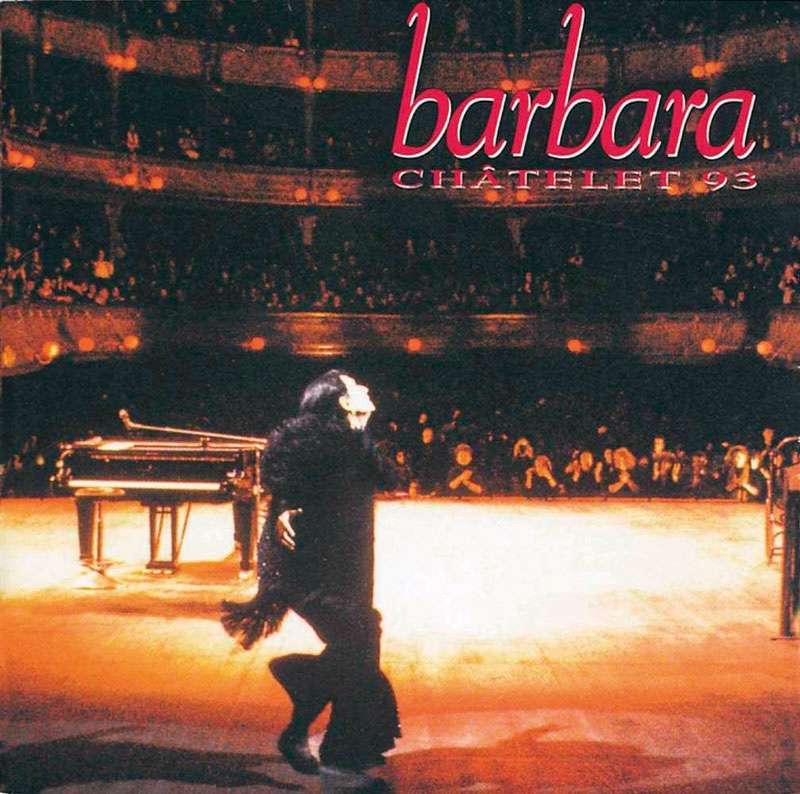浮世絵、海を渡る

1853年、日本開国。それまでにオランダ人がもたらした量とは比較にならないほどの規模で、19世紀後半、美術品から古道具と、さまざまな日本の工芸品がフランスに大量輸入されるようになり、パリではこれら »japonaiserie »
が大流行した。そのなかでも特に人気のあった浮世絵版画は、日本では安価で商品価値がなかったため、輸送中の品物を保護する包装紙として初めてフランスに来ることになった。
15世紀のフィレンツェや17世紀のローマに比べられるほど、芸術の中心都市だったその頃のパリ。方々からアーティストが集まり、アカデミックなテーマや技法とは違う独自の表現をそれぞれが模索していた。最初に浮世絵に注目したのは、マネを中心とする印象派の画家たちだ。彼らは、じかに目に映る光と色の「印象」を表現するために、ヨーロッパ伝統の技法−例えば陰影で立体感を出し、色を濁らせることがある−とはまったく違う方法概念を必要としていた。そこへ現われた浮世絵の、省略された線、平面的な色使い、色そのものの美しさは、晴天の霹靂。すべてが新鮮だった。
マネと同じく1863年のサロンへの出展を拒否された浮世絵狂のひとり、アメリカ人のホイッスラーは、その洗練された構図に注目し、フォルムと色のコンポジションを追究していく。また、モネの『ルーアンのカテドラル』や『睡蓮』などの、一定の主題を状況を変えてシリーズにするというアイデアは、北斎の『富嶽三十六景』によるところが大きい。そして、版画という表現手段における、色使い、描線、構図は、ロートレックの作品に代表される広告デザインの進展に貢献した。
ゴンクール兄弟の兄、作家エドモン・ゴンクールは19世紀美術の批評家でもあるが、その彼も、北斎と歌磨呂、2冊の解説入り浮世絵画集を出版してしまうほどに日本美術に魅せられてしまった。が、ゾラは »Le Naturalisme au Salon »(1880)にこう記す。「昨今誰もが持っている、明快で洗練された日本の版画は(…)印象派の画家たちに大きな影響を与えている。(…)我々の民族、環境のものではない芸術の模倣は不愉快な流行にすぎない。(…)あまりに素朴な単純化、平面的な色調の珍奇さ、凝りすぎの描線や色斑などは我々の創造性の粋としては受け入れられない。それは生きたものではない。我々は »生 »を表現するのだ。」 »誰もが持っている »ほど浮世絵はポピュラーだったらしいが、あまり出回ると、誇り高きフランス文化が浸食されてしまうと感じるのか?ただし、優れた芸術家は単なる模倣などに
は興味はない。
ゴンクールの画集を愛読し、弟のテオと浮世絵コレクションをしていたゴッホは、浮世絵の色を求めてアルルに移り住んだ。そこから
の手紙。「ライラック色の山を背景に(…)葡萄の植えられた、赤く素晴しい地表が見える。雪景色は真っ白な山頂が雪同様に輝く空に映え、まるで日本人が描いた冬のようだ。(…)親愛なる弟よ、僕は日本にいるような気分だ。」湿った日本と反対に、乾燥した気候の南仏で彼が見つけたという日本の色。でもそれは結局、彼自身が探していた色なのだろう。のちに、日本でも入手困難となった浮世絵のコレクションはやめるが、「自分の全作品は多少なりとも日本美術がベースになっている」と弟への手紙に書き、北斎の作品に深く感銘するゴッホ。「北斎の、草となでしこのデッサンは素晴しい。(…)日本の絵のこの上ない明瞭さがうらやましい。(…)楽々と何本かの確実な線で形を描く。ああ、何本かの線だけで形が描けるようにならなくては。この冬はそれに掛かりきりだろう。」自分なりに浮世絵の世界に浸り、そして独自の道を見つけていく。光と色の「印象」だけでなく、彼は、沸き起こる自分自身の「感情」も絵に定着させた。
1890年、37歳で自殺。
北斎が残した作品は、版画、スケッチ、肉筆画など合計4万点、出版物は210にも上る。流派に属さない一匹狼の生活は楽ではなかったが、彼は、庶民でも買える安価な版画を一生作り続けた。晩年出版した『彩色論』にこう記す。「絵が好きな子供たちに簡単な彩色方法を教えるため、(…)誰でも買える安いこの本で88年間の経験を伝える。」富嶽シリーズを制作したのは63歳から72歳。数え年75に出版した『富嶽百景』の序文から。「6歳から物の形を描くのに熱中した。50歳のころには数え切れないほどの版画を出版していたが、70歳より前に描いたものは数に入れる必要はない。73歳になって(…)自然の本当の構造が大体わかった。だから、80歳にはもっと進歩して、90歳には万物の神秘に分け入ることができ、100歳には極みに達し、そして110歳には、点ひとつにしろ、線一本にしろ、描いたものは全部動き出す。」ペリーの黒船が日本に来たのは、北斎が90歳で世を去って4年後のことだった。
(仙)