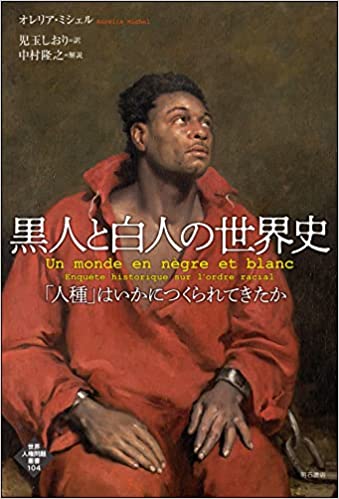
2020年5月の米テキサス州のジョージ・フロイド事件をきっかけに、ブラック・ライブズ・マター(BLM)運動が全米に広がり、世界各地に飛び火したとき、私はなぜ人種差別が21世紀になってもなくならないのか、そもそも人種差別はどのようにして生まれたのかと考えていた。ちょうどそのとき、ル・モンド紙の書評を読んで手にしたのが「Un monde en nègre et blanc – Enquête historique sur l’ordre racial」だった。
著者のオレリア・ミシェル氏はラテンアメリカ専門の歴史学者であり、黒人奴隷貿易と奴隷制の影響を受けた南北アメリカ文化圏についての講義をパリ=ディドロ大学で受け持ったのをきっかけにこの本を書いたという。一読して、これは人種の成り立ちを解明する画期的な本だと思い、是非日本の人たちに紹介したいと日本の出版社に提案した。その結果、幸運にも邦訳の運びとなった。
歴史学者だけあって、奴隷制の歴史を古代・中世からたどりつつ、黒人奴隷貿易、奴隷制プランテーション、植民地帝国主義と時代を下り、黒人差別(有色人種差別)の基礎となる「人種」という概念がどのように「作られて」いったかを解き明かしてくれる。
「奴隷制は人種差別から生まれたのではなく、人種差別が奴隷制に由来するものだ」という歴史家エリック・ウイリアムズの言葉のように、人種差別があったから奴隷制ができたのではなく、奴隷制によって黒人を差別する構図が生まれ、奴隷制廃止後も黒人に強制的な労働と劣悪な生活に甘んじることを強いるために、人種という概念が作り上げられたのだ。
そこには、産業革命によって大規模化するプランテーション、そして工業生産に安価な労働力が必要になるといった資本主義の要請がある。やがて欧州の大国が植民地支配に乗り出すアフリカやアジアでも、労働を強制するために「人種」が利用される。その図式は、現代の欧米諸国中心のエリートの支配する世界的な社会秩序につながっている。「人種」とは言えないかもしれないが、19世紀の蝦夷地、琉球の支配によって生じたアイヌ民族や琉球人への差別、明治以降に日本が採った欧米式帝国主義から生まれた朝鮮人、中国人に対する優越感情のからくりにも通じるものがあるように思う。
21世紀になっても人種は消滅するどころか、アメリカなどの白人至上主義、欧州では反ユダヤ主義、移民排斥運動といったナショナリストやポピュリストは再び力を盛り返そうとしている。なぜ科学的根拠もない「人種」が今もこれほどの暴力を生み出し続けるのか。「人種」の誕生を歴史的に掘り起こす本書を読むと、「目からウロコ」の連続なので、是非多くの人に読んでいただきたいと思う。(し)
「黒人と白人の世界史 ― 人種はいかにつくられてきたか」
オレリア・ミシェル著
児玉しおり訳
明石書店、2021年10月刊
*エスパスジャポンの図書館に所蔵。







