『 犬が尾から吠える場所(仮題) 』
Là où les chiens aboient par la queue
エステル=サラ・ビュル著 / Editions Liana Levi刊
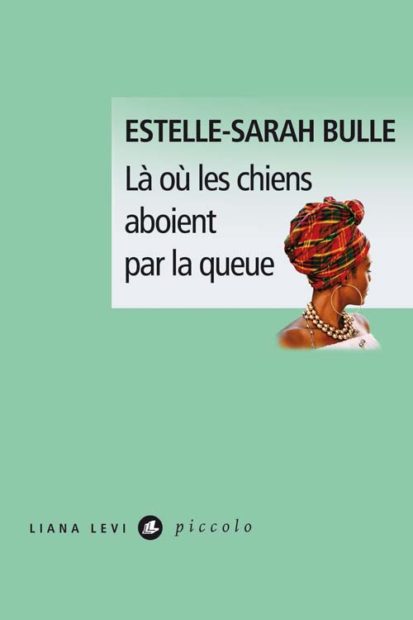
家族のルーツを求めて
1960年代初頭。フランス政府は深刻な経済的危機に陥った海外県の状況に応じるため、BUMIDOM(海外県における移住発展のための部局)を設立し、雇用を約束しながら本土への移住を奨励する政策を採った。80年代初頭までに、より良い未来を期待して海を渡った海外県の人々の数は7万人以上とも言われる。だが彼らの多くは社会的地位の低い従属的な職業しか与えられない現実に失望する結果となり、BUMIDOMは批判の的となった。最近、この政策によって70年代に移住し強盗団となった若者たちの実話に基づいた映画『Le Gang des Antillais』(2016年)によって、この制度についての議論が再燃したことも記憶に新しい。
この本の主要な登場人物となるエゼキエル姉弟は、みな60年代にグアドループから移住した人々だ。彼らが生まれたのは、モルヌ・ガランという島の中でも辺境にあたる地域で、住人と牛しかいない砂漠のようなその場所を、現在でもグアドループの人々は「犬が尾から吠える場所」(現地のクレオール語で「僻地」の意)と呼ぶらしい。
著者はパリ南東の郊外クレテイユで、グアドループ出身の父とフランス北部出身の母との間に生まれた。彼女は父の家族の歴史を探るために、父と二人の姉妹に聞き取りを行った。自伝的な文章と家族による語りが組合わされてできたこの作品は、ある家族の物語であると同時に、アンティル諸島からフランスへ渡った何万もの無名の人々が共有する移住の経験の、貴重な証言でもある。
小さな島と大きな歴史。
私たちがグアドループの歴史に惹かれるとすれば、それはカリブ海のこの小さな場所が、海を越えた広い世界へと縦横無尽に繋がり、それを知った私たちの視野まで広げてくれるからだろう。こうした地域では、家族の歴史が、まるで壮大な世界史を収縮したような形で現れるのだ。三人の姉弟は、奴隷の子孫である父と、18世紀にグアドループに渡ったブルターニュの人々の末裔である母を持った。奴隷制から人種差別が明白に存在する社会で、二つの家族間の関係は決して良くはなかった。家族内でもそう上手くはいかず、例えば姉弟の母は、アントワーヌより明るい肌で生まれ、より小柄な体だったルシンドをより可愛がっていた、という具合である。
移住という経験。
けれども、姉弟の中で際立つのはアントワーヌだった。彼女は自分の意志で突き進む。田舎から都会へ、都会からカリブ海、そしてパリへ。誰にも従わず、自由に振る舞い、ブテッィク経営という目標に自力で到達した。物語の、そして家族の中心は彼女にある。面白いのは、まるで黒澤明の映画『羅生門』のように、ときに矛盾しさえする三人の証言によって、複数の視点から物語が作られていくところだ。つまり一つの事柄について複数の解釈が存在する。同時に、移住という経験が各自にとっていかに異なっていたかも示される。それは67年5月、グアドループで起きた出来事についてアントワーヌが証言する場面だ。昇給を求めストを起こした労働者たちに対し、死者を伴う激しい弾圧を警察隊が行った。しかしこの重大事を、グアドループから既に離れていた著者の父は知らなかった。彼の周りの誰もこの小さな島の出来事について語らなかったからである。アントワーヌがパリに移住するのはその翌年。彼女の弟や妹と異なり、彼女が故郷を去る決定的契機となったのは、グアドループ社会の現実を象徴するこの流血の惨事だった。
これは一つの家族の物語であり、特殊な一例に過ぎない。けれども、例えばパリに暮らすとき、私たちがこうした地域から来た人々と接することは決して稀ではない。もしそうした機会があるなら、彼らがどこからやって来たのか、なぜここにいるのか、その経緯に思いを馳せてみるのも悪くないのではなかろうか。(須)

Estelle-Sarah BULLE – ©Julien
エステル=サラ・ビュル
1974 年、パリ郊外クレテイユに生まれる。コンサルタント業や文化施設などでの仕事を経て現在に至る。初の小説作品となる本作でスタニスラス賞を受賞。







