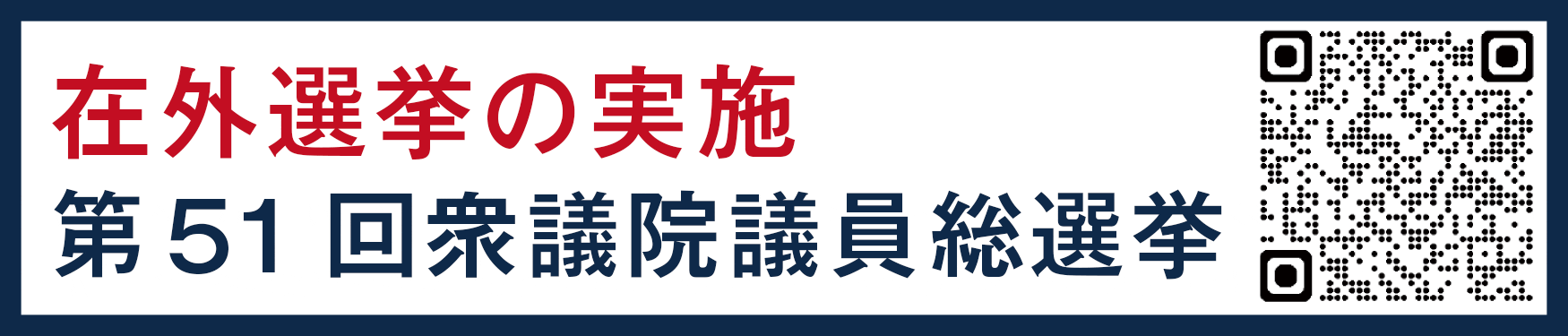監督・脚本家・俳優としてボーダーレスな活躍を続けるジュリー・デルピー。彼女の長編7作目となる自作自演の映画『My Zoé』が、ようやくフランスで公開(6月30日)となった。本作は2018年に撮影が開始し、2019年にカナダやスイス、ドイツで劇場公開されるも、コロナ禍で世界配給のスケジュールが大幅に乱れた。フランスでも劇場閉鎖に伴い延期に。しかしその遅れを取り戻すかのように、現在パリのシネマテーク・フランセーズでは、彼女の仕事をふり返るレトロスペクティブを開催中(7月3日迄)だ。作品ごとにジャンルや作風を変えながら新たな表現に挑むデルピーを、シネマテークは「アンチコンフォルミスト(反順応主義者)」と讃える。
新作『My Zoé』では新しいタイプの家族ドラマを手がけた。もともと「科学者になりたい」と思っていたというデルピーは、自身が演じる主人公イザベルを、ラボに勤める免疫遺伝学の専門家とした。この設定はドラマで大きな意味を持つ。
イザベルは7歳の愛娘ゾエと暮らす。前夫とは子供の預かり問題などで小競り合いが絶えない。ある朝、ゾエは目を覚まさない。意識を失っているのだ。そしてイザベルの思いも寄らぬ闘いの日々が始まる。

“生命の危機に立つ子どものために奮闘する親”という役柄は、フランスでヒットを記録したヴァレリー・ドンゼッリの主演・監督作品『私たちの宣戦布告』(2010年)と重なる。しかし、『私たちの宣戦布告』が音楽を積極利用したメロドラマであったのに対し、こちらは禁欲なまでに音楽に背を向ける。ただし、感情が動かされるポイントのひとつが、「触れる」というシンプルな行為だ。コロナ禍で人々が互いに触れ合いにくい時代に、「髪を撫でる」「頰に触れる」といった静かな愛情表現が、さらに印象的に浮き上がってくるようだ。
この映画は生命倫理の問題に抵触する。イザベルの選択はおそらく賛否両論だろう。しかし逃げも隠れもせずにドラマを介してタブーに切り込み、問題提議さえ促してしまう姿勢は全く肝が座っている。そもそも本作は「子どもの生命の危機」という、親であれば最も見たくないものを取り上げているし、前作『La Comtesse 血の伯爵夫人』でも、「美と若さへの執着」という特に女性にとってはあまり深入りしたくないテーマを正面から取り上げていた。
見たくないものから目を逸らさず、あえて立ち向かってゆくのがデルピー流なのだろうか。80年代から90年代にかけ、ゴダール、カラックス、キェシロフスキら鬼才の作品に登場し、スクリーンの華となっていた女優時代からは予想不可能な転身ぶりでもあり、その計り知れない逞しさには期待感しかない。(瑞)